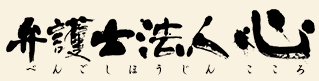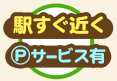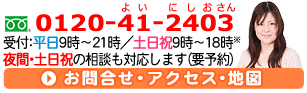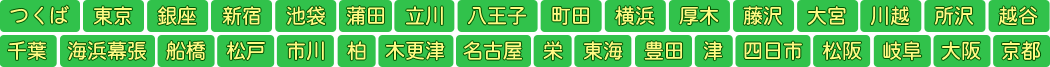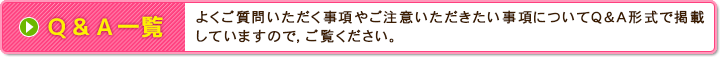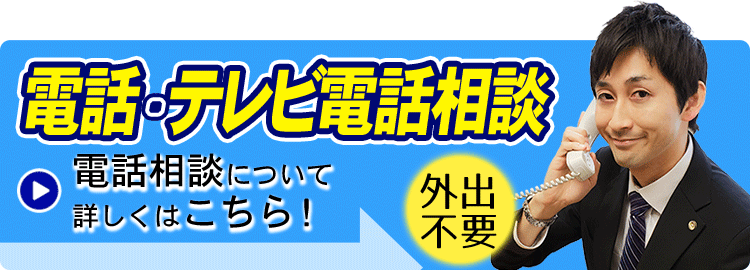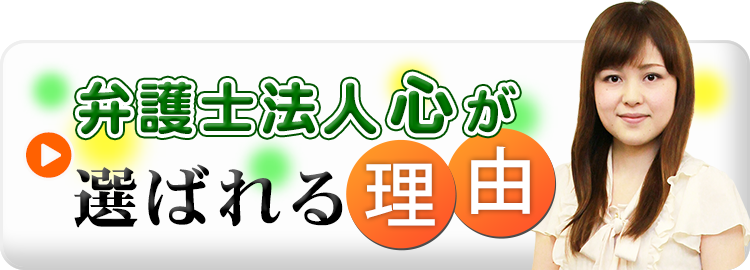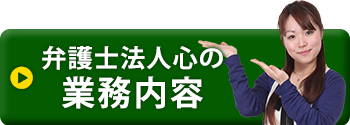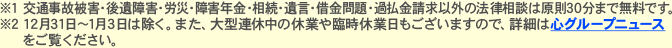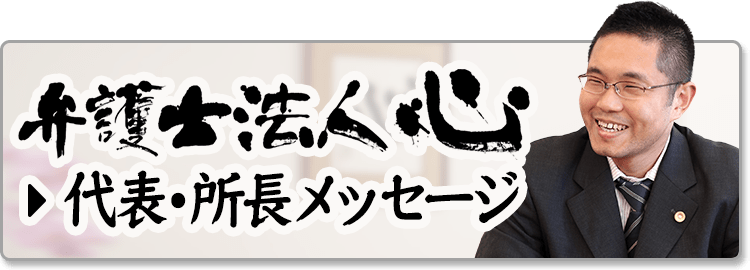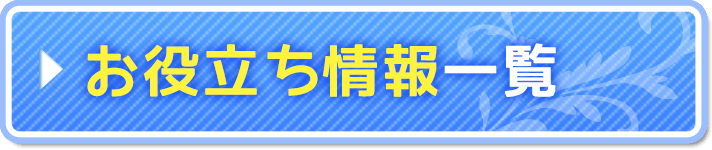自転車と道路交通法
1 自転車についての規制の強化
平成29年に行われた道路交通法改正により、自転車の交通に関する規制が強化されました。
後記で記載するような違反行為(※後記では紙幅の関係上一部の違反行為のみ抜粋して記載します。)を反復して行った場合で、公安委員会が、更に自転車を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、自転車運転者講習を受けなければなりません(道路交通法108条の3の5第2項)。
自転車は多くの方が手軽に利用できるものですが、乗る場合はしっかりとルールを確認しておくことが大切です。
また、自転車であっても、道路交通法に違反すると懲役刑や罰金が科される場合がありますので、ご注意ください。
参考リンク:警視庁・自転車の交通ルール
2 自転車に適用される道路交通法の主な規制
自転車にも適用される道路交通法の主要な規制を列挙すると、以下のとおりとなります。
- ①信号に従い走行する義務(道路交通法7条)
- ②通行禁止に関する規制(道路交通法8条)
- ③通行区分に関する規制(道路交通法17条)
- ④路側帯通行における規制(道路交通法17条の2)
- ⑤並進の禁止(道路交通法19条)
- ⑥交差点における他の車両等との関係に関する安全走行義務(道路交通法36条)
- ⑦指定場所における一時停止義務(道路交通法43条)
- ⑧車両等の灯火義務(道路交通法52条)
- ⑨歩道通行時の通行方法の規制(道路交通法63条の4)
- ⑩酒酔い運転に関する規制(道路交通法65条第1項)
- ⑪安全運転義務(道路交通法70条)
- ⑫運転者の遵守事項(道路交通法71条)
その中でも、一般の方で特に注意すべき規制としては、まず、自転車は原則として車道を走らなくてはならないということです。
また、自転車が2台以上並んで走る「並走」も道路交通法で原則禁止されています(上記⑤)。
夜間に自転車を運転される方も多いかと思いますが、夜間無灯火で自転車を運転することも禁止されています(上記⑧)。
お酒を飲んだ場合や過度に疲れている場合、薬を飲んで眠気がある場合にも、自転車を運転することは禁止されています(上記⑩)。
その他にも、雨の日に傘をさして運転することや、携帯電話を使いながらの運転も禁止されています(上記⑫)。
また、イヤホンで音楽を聴きながら自転車を運転することの禁止や、ブレーキのない自転車を運転することの禁止といったものもあります(上記⑫)。
なお、令和6年の道路交通法改正により、「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」に関して罰則が強化されました。
参考リンク:警視庁・自転車に関する道路交通法の改正について