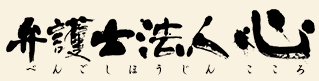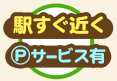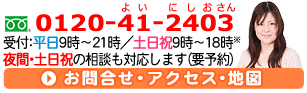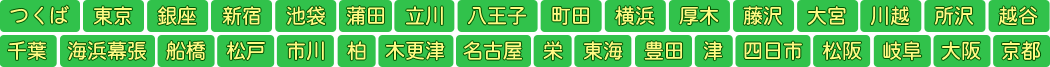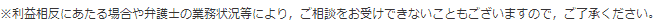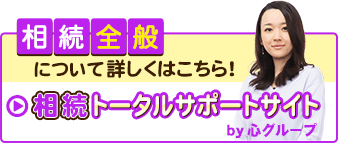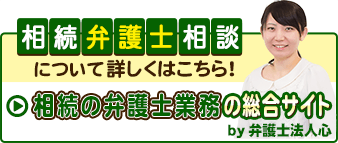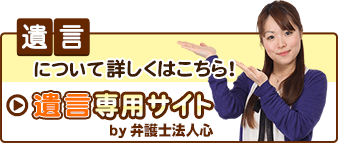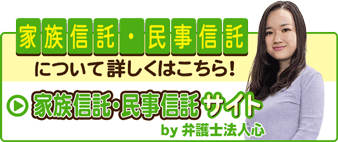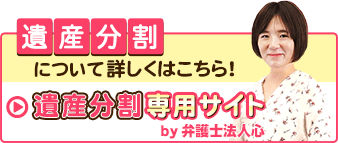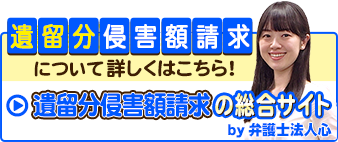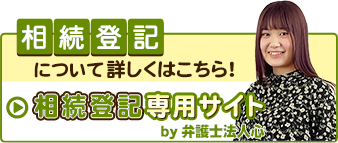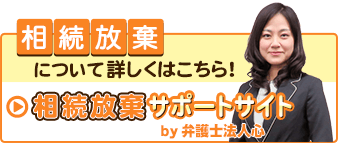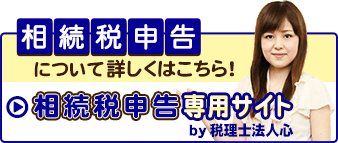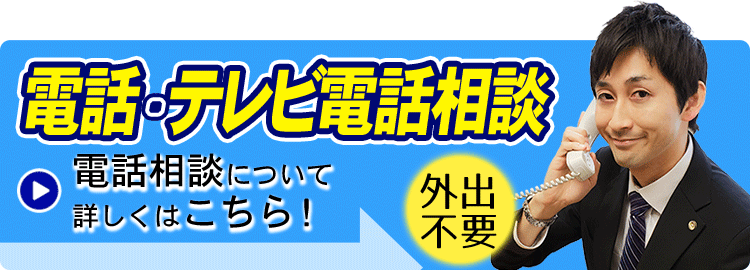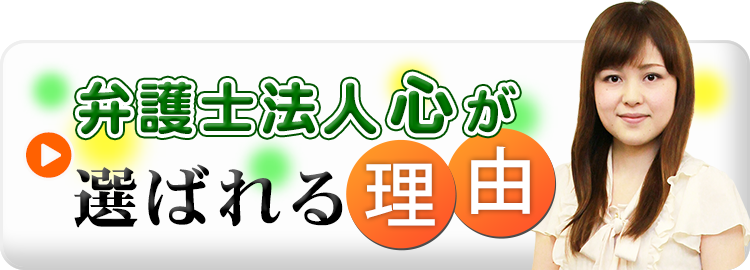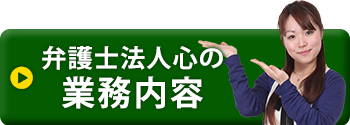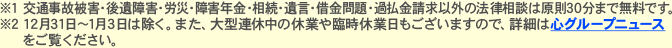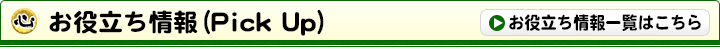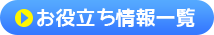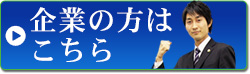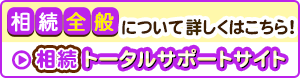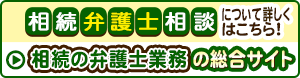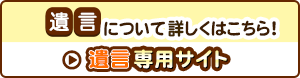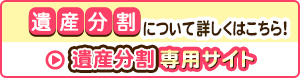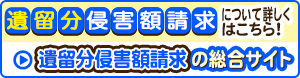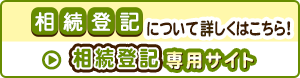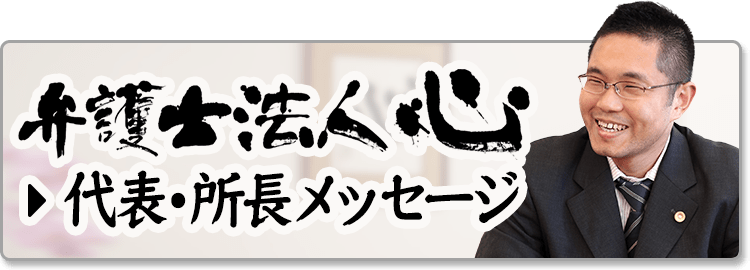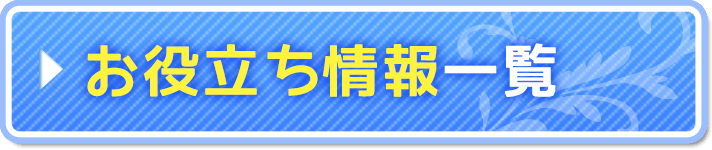相続・遺言
電車でお越しいただけます
相続に関するお悩みは、当法人へご相談ください。事務所が名古屋駅の近くにありますので、ご来所の際も地下鉄やJR、名鉄などでお越しいただきやすいかと思います。
相続を得意とする弁護士と苦手な弁護士の違い
1 いわゆる相続法は択一試験でしか勉強しない

弁護士は、司法試験を経て弁護士の資格を得ていますが、司法試験では民法のうち相続に関する法律は択一試験でしかでないことがほとんどです。
論文試験に相続が出題されることはほとんどありません。
そのため、弁護士になった時点では、相続に関する法律に詳しい弁護士はほとんどいないのが現状です。
2 相続を集中的に取り扱うことで得意分野化
弁護士のところには、相続のほかにも自動車事故、借金に関する問題、中小企業相談など、様々な分野の相談が寄せられます。
多くの弁護士事務所では、一人の弁護士があらゆる分野の相談にのっているのが現状です。
そのため、一人の弁護士が年間で取り扱う相続の件数は数件程度というところも少なくありません。
しかし、弁護士事務所によっては、分野ごとの担当制としており、相続分野を担当している弁護士が相続を集中的に取り扱うということを決めている事務所もあります。
そのような弁護士事務所の場合、一人の弁護士が年間で取り扱う相続の件数も数百件単位になりますので、必然的に経験数も増えて、得意分野となります。
3 得意分野をイチから調べたりはしない
弁護士は、案件のご依頼を受けた場合、まずは関連する法令や裁判例の調査を行います。
関連法令や裁判例の数は膨大に存在しますので、これだけでも相当な時間がかかります。
しかし、相続案件を得意とする弁護士は、普段から相続案件を取り扱っていますので、イチから調べる必要がなく、すぐに案件解決のために行動することができる点が強みです。
4 相続に関する法改正や最新の裁判例にも精通
日常的に相続を扱っている弁護士は、法改正や最新の裁判例の動向にも非常に敏感になっていますので、常に最新の情報を把握し、理解するよう努めています。
相続を苦手としていたり、あまり取り扱っていない弁護士の場合、最新情報を把握する必要性がありませんので、どうしても情報が古くなりがちです。
相続で困った場合は弁護士にご相談を
1 相続を弁護士に相談するとよい理由

相続を相談できる専門家は、複数おりますが、紛争になっている案件を扱うことができるのは、原則として弁護士だけです。
このような規制がある理由は、法律に詳しくない人のアドバイスに従った結果、損をしてしまうというような事態を避けることにあります。
そのため、相続で困ったことがあった場合は、まず弁護士にご相談ください。
費用が心配という方は、無料相談を行っている弁護士に相談すると安心です。
2 弁護士の選び方
相続の相談は弁護士にすべきではありますが、弁護士であれば、誰であっても安心かというと、必ずしもそうとは言えない場合があります。
たとえば、普段は企業同士の契約書のチェックなどを主に行っている弁護士であれば、相続の取扱件数は少ないかもしれません。
あまり相続の案件を扱ったことがない場合、相続に関する知識やノウハウが十分でない可能性があります。
そのため、相続について弁護士に相談する場合であっても、どの弁護士を選ぶかは、慎重に見極める必要があります。
相続を得意としている弁護士であるかどうかを確認することが大切です。
3 相続に強い弁護士の特徴
⑴ 相続を中心に取り扱っている
法律の中には、様々な分野がありますが、当然特定の分野を集中的に扱えば、その分野の実績が積み重なります。
多くの実績が積み重なれば、交渉のノウハウ、裁判手続きになった場合の見通しなどが洗練され、よりよい解決方法を探し出すことが可能です。
⑵ 相続チームで事件を扱っている
仮に、相続を中心に扱っている弁護士であっても、弁護士1人で扱うことができる案件の数は限られています。
しかし、相続を中心に扱っている弁護士が、チームを組んでいる場合は、そのチームの人数分のノウハウが蓄積されます。
その結果、1人で案件を扱っている弁護士より、多くのノウハウを習得することができます。
⑶ 税金についても詳しい
相続を扱う以上、税金についても知識も不可欠です。
たとえば、遺産の分け方を決める際には、誰にどのような税金が発生するかという観点も必要になります。
相続に強い弁護士であれば、そういった税金についてもノウハウを蓄積しています。
弁護士に依頼した場合の相続財産の調査方法
1 特別な権限で戸籍を集めます

相続財産は、あくまで亡くなった方の財産であるため、たとえ家族であっても、勝手に調べることはできないのが原則です。
ただし、相続人は、亡くなった方の権限を受け継いでいるため、例外的に相続財産の調査が可能です。
そこで、相続財産の調査をする際には、まずは「相続人であることの証明」が必要になります。
「相続人であることの証明」は、戸籍謄本によって行います。
戸籍謄本は、市区町村で管理されているため、全国の役所から取り寄せる必要があります。
場合によっては、明治時代まで遡って、戸籍を取得することになります。
役所は、窓口に来た人自身の戸籍や、親子間の戸籍については、比較的スムーズに発行してくれますが、兄弟姉妹などの戸籍の発行については、すぐには発行してくれないことがあります。
しかし、弁護士であれば、特別な権限で、戸籍を取得することができます。
2 法定相続情報の取得
相続人であることの証明をするためには、戸籍謄本を、相続財産を管理する機関などに提出しなければなりません。
しかし、提出した戸籍は、必ずしも返却してくれるとは限りません。
また、郵送で手続きをする場合は、提出した戸籍謄本が郵送で返却されるまでは、他の機関で調査をすることができず、非常に不便です。
このような事態を避けるために、戸籍謄本を複数枚取得する方法もありますが、役所に支払う手数料が余分にかかってしまいます。
そこで、弁護士が相続財産調査をする場合は、法務局で法定相続情報という書類を取得します。
この書類は、相続人であることの証明として、戸籍謄本の代わりになるもので、何枚でも無料で発行できます。
この法定相続情報があれば、相続財産調査がスピーディーに進みます。
3 預貯金の調査
相続財産の代表的なものとして、預貯金があります。
預貯金を一元的に管理している機関はないため、各銀行などを個別に調査する必要があります。
まず、手がかりになるのが、亡くなった方が所有していたキャッシュカードや通帳です。
取引していた銀行などが分かれば、その取引履歴を取り寄せ、他の金融機関との取引がないかを調べます。
全く手掛かりがない場合は、亡くなった方が居住していた付近の金融機関に目星をつけ、調査するといった方法もあります。
弁護士は、職権でこれらの金融機関・支店に対して亡くなった方の預貯金口座がないか調査を行うことができます。
4 不動産の調査
不動産は、高額な財産であるため、亡くなった方が不動産を所有しているかどうかは、相続財産の調査の中でも、非常に重要度が高いといえます。
不動産の調査方法として、まずは毎年4月頃に市区町村役場から送付される、固定資産税に関する通知が、手がかりになります。
ただし、固定資産税に関する通知は、不動産に共有者がいる場合、代表者にのみ送付されることが多いため、注意が必要です。
特に、先祖代々の不動産があるような場合、亡くなった方が、他の親戚と共有している不動産が、どこかにあるかもしれません。
そういったケースでは、亡くなった方のご両親や祖父母の、今までの住所などを調べ、そこの市区町村に問い合わせをして、不動産の有無を調べることになります。
弁護士は、土地・建物等の不動産について、各地方自治体に対し、職権で調査を行うことできます。
名寄帳を取り寄せた後、必要性に応じて法務局から登記簿謄本を取り寄せ、亡くなった方の持分等を含め、調査を行います。
5 株式の調査
亡くなった方が、株式を所有していた可能性がある場合、株式の調査も必要になります。
株式を扱っている証券会社が分かっているのであれば、その証券会社に問い合わせをして、どのような銘柄の株式があるかを調査します。
株式の名義変更を行う場合は、相続人も株式の口座を開設する必要があるため、お近くの証券会社で手続きを行わなければなりません。
もし、証券会社が分からない場合や、そもそも株式を持っていたかが分からないような場合は、証券保管振替機構に問い合わせをします。
証券保管振替機構は、上場株式を一元的に管理しており、弁護士は職権で調査をすることができるため、株式の有無を調査することができます。
他方、亡くなった方が所有していた株式が、非上場株式だった場合は、その会社に対して、株式の詳細を問い合わせることになります。
6 債務の調査
亡くなった方の、債務についても、調査をしておかないと、「結果的に債務の方が多くて、損をした」という事態になりかねませんし、借金の有無は、そもそも相続すべきか、相続を放棄すべきかの判断が必要となりますが、相続放棄は基本的に亡くなってから3か月以内にしなければなりませんので、速やかな対応が必要です。
債務の調査は、まず信用情報機関に借金の有無を問い合わせることから始まります。
信用情報機関とは、消費者金融などからの借り入れを管理している機関をいいます。
日本にある信用情報機関は、「CIC」、「JICC」「KSC」の3つがあるため、その3つの機関で債務の調査を行います。
もっとも、勤め先からの借り入れや、友人などからの借り入れ情報は、信用情報機関に登録されていないため、信用情報機関に問い合わせをしただけでは、全ての債務は分かりません。
そのため、亡くなった方の家にある書類や、通帳などから、債務の有無を調査することになります。
7 生命保険の調査
亡くなった方が契約者となった生命保険について、弁護士は職権で生命保険協会に問い合わせて確認することができますので、その手続きを行います。
弁護士による相続人の調査
1 相続で調査しなければならないこと

相続についての話し合いを行う際には、必ず相続人全員と連絡を取り、誰がどのように相続財産を取得するかを合意する必要があります。
連絡をとることができなかったり、合意に加わることができなかったりする相続人がいると、有効な合意とは扱われず、相続の手続を進めることは一切できなくなってしまいます。
もし、相続人が他にもいることに気がつかないまま、遺産分割協議を終わらせてしまうと、再度、遺産分割協議をやり直さなければならなくなってしまうこともあります。
ここでネックになってくるのが、相続人が誰であるかが分からない場合、どのようにして相続人を特定するか、相続人がどこに住んでいるか分からない場合、どのようにして住所を特定するかです。
これらの調査については、弁護士に委ねることもできます。
以下では、弁護士がこのような調査するときの流れを説明したいと思います。
2 相続人が誰であるかの調査
相続人が誰であるかを調査する場合、相続人を特定するための戸籍を一通り取得する必要があります。
具体的には、亡くなった方が生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍謄本を揃える必要があります。
弁護士は、職務上の必要があれば、相続人を特定するための戸籍を取得することができることとなっています。
このため、相続人の調査をご依頼いただいた場合は、弁護士は、各地の市町村役場とやり取りし、必要な戸籍を取得し、相続関係を特定することとなります。
相続人が自ら集めることもできますが、コンピュータ化される前の戸籍謄本は、手書きで書かれており、大字、変体仮名、異体字といった、慣れない方が読もうと思ってもなかなか読み解けない字で記載されていることもよくあります。
相続案件をよく取扱う弁護士は、これらの字にも慣れておりますので、スピーディーに戸籍謄本を取り寄せることができます。
3 相続人がどこに住んでいるかの調査
相続人がどこに住んでいるかを調査する場合は、相続人の住民票か戸籍の付票を取得することで、相続人の住民票上の住所がどこにあるかを確認することが考えられます。
この場合も、弁護士は、職務上の必要があれば、相続人の住民票や戸籍の付票を取得することができます。
弁護士は、戸籍の取得と合わせて、各地の市町村役場とやり取りして必要な住民票や戸籍の付票を取得し、相続人の住所を特定することとなります。
ここで問題となるのが、相続人が住民票上の住所に住んでいない場合です。
このような場合であっても、住民票上の住所の近隣に住んでいる人に確認すると、相続人の引っ越し先等が判明することもあります。
このため、住民票上の住所の近隣に住んでいる人に確認する方法も考えられるところです。
ただ、このような方法は、プライバシー等の問題が生じるおそれがあるため、用いる場面は限られています。
4 弁護士への相続人調査の依頼
このように、弁護士に相続人調査を依頼することで、相続人が誰であるか、相続人がどこに住んでいるかを特定することもできます。
相続では、数次相続が起きている場合など、相続人の人数が数十人になることもありますので、個人の方が相続人調査を完結することが難しいこともあります。
相続人の調査でお困りの場合は、弁護士にご相談ください。
相続に強い弁護士にご相談ください
1 法律には多種多様な分野があります

六法全書という言葉から、法律は6つ程度しか種類がないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、日本には、民法や刑法など、法律と呼ばれるものが、約2000前後存在します。
たとえば、その中の1つである民法は、第1条から順番に規定が置かれ、トータルでは1000条を超える条文が定められています。
このように、法律はとてもジャンルが多彩であるため、全ての分野に詳しくなるのは、困難と言えます。
そのため、仮に国家資格を有している弁護士であっても、その弁護士が、相続に詳しいとは限りません。
そこで、相続について相談するのであれば、相続に強い弁護士に相談することが大切です。
2 相続に強い弁護士に相談するメリット
⑴ 相談がスムーズに進む
弁護士に相談する際、相談者の方は、今の不安な点や、今後の見通しについて、弁護士にアドバイスを求めることになります。
しかし、相続に詳しくない弁護士に相談した場合、質問されたことにすぐに回答できなかったり、経験の少なさから、適切な見通しを立てることができなかったりする可能性があります。
他方、相続の分野を集中的に取り扱っている弁護士であれば、相続の場面で問題になることや、解決方法について詳しいため、相談時の質問に的確かつスピーディーに回答し、今後の見通しをアドバイスすることが可能です。
⑵ 未来を見据えたアドバイスができる
相続の場面でもめ事になってしまった場合、最終的には裁判所での手続きが必要になります。
裁判になった場合、裁判官を説得するための証拠をどれだけ用意できるかで、裁判の結果が大きく左右されます。
とはいえ、弱い証拠をたくさん集めても有利になるとは限らないため、裁判官を説得し得る強い証拠を集めることが大切です。
相続に強い弁護士であれば、どのような証拠が、裁判官を説得できるのかという点にも詳しいため、相談の初期段階から、有利な証拠集めを開始できます。
⑶ 税金についても配慮した適切な提案
相続に強い弁護士であれば、相続と税金が深く関わっていることを知っています。
どのタイミングで、どのような税金が発生するのかを知っておかないと、税金の申告を怠ってしまい、結果として余計な税金を課せられるといった不利益が発生しかねません。
相続を扱っている弁護士の中には、税理士資格も持っている者がいます。
そのような者に相談すれば、弁護士兼税理士として、相続における税金面を踏まえた適切な提案をしてもらえます。
弁護士に相続の相談をする際の流れ
1 まずは相続に強い弁護士を探す

アメリカなどの訴訟大国では、弁護士は各担当分野を決めて、その分野に集中的に取り組むことが多いですが、日本では1人の弁護士が複数の分野を扱うケースが多くあります。
そのため、数ある法律の分野の中でも、相続を集中的に取り扱う弁護士は、それほど多くはいないかもしれません。
相続について弁護士に相談することは、一生に一度あるかないかの大事な場面ですので、相談する際は、相続に強い弁護士を探すことが大切です。
相続に強い弁護士であるかについての判断は、相続についての専門のホームページがあるかどうかが、1つの目安になります。
事務所のホームページ以外に、特定の分野に特化したホームページがあるということは、その法律事務所は、その分野に特に力を入れていることの表れといえるからです。
そのため、まずはインターネットなどを利用して、相続専門のホームページがある法律事務所を探すとよいかと思います。
2 事務所に問い合わせをする
弁護士は、裁判等で事務所を不在にしていることも多いため、法律事務所に予約なしで訪れても、弁護士に会えない可能性があります。
そのため、法律相談をする際は、まず事務所に電話やメールをして、相談の予約を取ることになります。
その際、ご不安な点等、どのようなことを相談したいかについて、あらかじめ伝えておくと、弁護士への相談がスムーズに進みます。
問い合わせをする際は、電話相談が可能なのかどうかや、ご自宅から通いやすい場所に事務所があるかどうかも確認することをおすすめします。
名古屋にお住まいの方や、職場が名古屋にある方は、名古屋市内にある法律事務所に相談すると便利です。
3 相談の日の流れ
⑴ 事務所での相談の場合
事務所にお越しいただき、弁護士と相談をすることになります。
弁護士は、相談者様が不安に思っていることについて、法的な観点からアドバイスをしたり、今後の見通しについて説明をしたりします。
また、相続について相談する場合は、遺産に関する資料などを用意しておくと、相談がスムーズに進みます。
もし、銀行や法務局で資料を用意することが難しい場合は、メモなどに遺産の概要を記載したり、質問したいことをまとめたりすると、相談当日に慌てることが少なくなります。
⑵ 電話での相談の場合
最近は、電話での相談を受け付けている法律事務所もあります。
電話相談の場合、共通の資料を見ながら相談することが難しいため、あらかじめ資料を手元に置いて、相談したいことをまとめておくと、相談がスムーズに進みます。
また、テレビ電話を活用するなどして、共通の資料を見ながら相談することも可能です。
各専門家が協力できることの強み
1 相続は複数の分野の専門家が必要です

通常、専門家に特定のお悩みを相談する場合、その問題だけ解決できればいいため、その特定の分野の専門家に相談すれば、問題は解決するかもしれません。
しかし、相続は、一人の方が亡くなった時にその方が残した財産を全て承継するための制度です。
つまり、亡くなった方に関する全ての問題を、一度に解決する必要があります。
例えば、「うちは相続税がかからないから、相続税のことは特に気にしなくて大丈夫。兄弟でもめないようにだけ、対策を採って欲しい。」などとご相談を受けることもあります。
実際には、よくよくお話をうかがってみると、毎年4月頃に送られてくる固定資産税の通知書を見て、自分の不動産の評価額を把握し、インターネット等で基礎控除額を計算し、相続税がかからないと判断されていました。
ただ、固定資産税の評価額と相続税の評価額は異なりますし、特に、農地や雑種地が存在する場合は、固定資産税評価額は非常に安くなっていても、相続税評価額になおして計算してみると、数十倍もの額になることもあります。
ですので、相続では、紛争解決のみ相談したい、相続税だけ相談したいなどの特定の分野に偏ることなく、各専門家が協力し合い、全ての問題を解決することが大切です。
2 紛争案件で特定の分野の専門家が欠けてしまった場合のリスク
例えば、相続人同士で、遺産を巡ってもめごとになり、裁判所で決着をつけることになった場合、弁護士の協力が必要です。
しかし、相続の場面では、相続税や譲渡所得税といった問題も考慮に入れなければ、適切な問題解決を図ることはできません。
そのため、相続について問題を解決する場合、税理士の協力も必要になります。
その他にも、遺産を巡って争いになった場合、不動産をどのように分けるかが、大きな問題になります。
もし、不動産の評価額を適切に判断できなければ、遺産の分け方で不平等な結果になることがあります。
そのため、相続の場面では、宅建士などの不動産に関する専門家の協力も必要になります。
このように、相続の問題を解決するためには、各専門家が協力体制を作り、トータルサポートを実現しなければ、適切な解決は難しくなります。
3 生前対策で特定の専門家が欠けてしまった場合のリスク
生前対策を行う場合、将来発生するであろう相続税を見据えつつ、不動産や保険金を活用した生前対策を行い、相続人が相続税を支払えるようにしておく必要があります。
こういった対策をする場合、税理士の協力がなければ、適切な対策は難しくなります。
また、遺族がもめないようにするためには、遺言書等で対策を打っておく必要がありますが、遺言書の内容によっては、かえって相続人間で紛争を起こしてしまう可能性があります。
こういった対策をする場合、遺言書に関する裁判を多く扱っている弁護士の協力がなければ、遺言書があるせいで、もめ事が大きくなってしまう可能性があります。
4 各専門家が協力している強み
各専門家が協力して、相続のトータルサポートをしていれば、上記のようなリスクに対応し、適切に問題を解決したり紛争を予防したりことができます。
相続について相談するのであれば、各専門家が協力して、相続の問題を集中的に取り扱っているところに相談することをおすすめします。
相続でよくあるお悩み
1 相続のお悩みは大きく分けると二種類
相続のお悩みは、大きく分けると、「ご生前の相続対策」「ご逝去後の遺産の取り分」に分けられます。
それぞれのお悩みの内容や対策について、以下でご説明いたします。
2 ご生前の対策について

⑴ よくあるお悩み
例えば、ある相続人には遺産を渡したくない、前妻の子にもある程度遺産を渡してあげたい、子どもがいないから妻が困らないようにしたいなどのご相談にのらせていただくことがあります。
⑵ 対策として遺言書の作成がおすすめ
上記のお悩みのいずれも解決することができるのは遺言書ですので、まずは遺言書を作成されることをおすすめします。
遺言書を作成する場合、自筆で作成する遺言と公証役場で作成する遺言で悩まれることがありますが、それぞれメリット・デメリットがありますので、相続に詳しい弁護士にご相談ください。
⑶ 遺言書とあわせて財産管理契約・任意後見契約・信託契約等も検討
遺言書だけでは解決できず、財産管理契約・任意後見契約・信託契約等をセットで行った方がよいこともありますので、相続に詳しい弁護士から提案してもらうことをおすすめします。
3 ご逝去後について
⑴ よくあるお悩み
相続のご相談内容として、紛争になるケースと紛争にならないケースに分けられます。
紛争になるケースでは、遺言書の無効を争いたい、せめて遺留分は確保したい、他の相続人は生前に大量の贈与を受けていたから自分の取り分はもう少し多いのではないかなど、遺産の取り分に関するご相談が寄せられます。
紛争にならないケースでは、不動産の名義変更や、預貯金の解約手続き、自動車の名義変更、遺言の執行手続、相続放棄をしたいなどのご相談がよせられています。
⑵ 紛争になるケースの場合
まずは、話し合いでの解決を目指します。
それでもまとまらなければ、調停や審判、訴訟手続きを行います。
一度、家族で話し合ってみますという方もいらっしゃいますが、ご家族で協議を行い、こじれてしまってからご相談に来られると解決までに非常に時間がかかることがありますので、無料相談を行っている弁護士等に、まずはそれぞれの遺産の取り分が法的にはどれくらい認められるのか等を相談してみるとよいかと思います。
相談する弁護士を見つける際には、相続に関する裁判を多く扱っている弁護士に相談すべきです。
また、税金面でも有利に交渉を進めるために、税金にも詳しいかどうかもご確認ください。
⑶ 紛争にならないケース
紛争にならないケースでは、納税資金の確保等のため、速やかな手続きの実行が求められます。
金融機関等での払戻し手続だけでなく、不動産の場合は登記名義の変更、税金の場合は相続税の申告手続きが必要となりますので、登記手続きや税金関連の手続きに関しても、トータルに取り扱ってくれるところがおすすめです。
相続放棄をお考えの場合、一刻も早く相続に詳しい弁護士に相談してください。
相続放棄は、原則として亡くなってから3か月以内でなければ手続きを行うことができません。
期限がギリギリであれば、家庭裁判所に期限伸長の申立て手続を速やかに行わなければなりませんので、急ぎ、弁護士に相談されることをおすすめします。
相続人が行方不明の場合の対応方法
1 行方不明の相続人を探す方法

⑴ 戸籍の附票を確認します
戸籍の附票には、現在に至るまでの住民票の履歴が載っていますので、音信不通で住所が分からない場合でも、本籍地が分かれば戸籍の附票によって住民票上の住所地を知ることができます。
⑵ 戸籍の附票の請求は弁護士に依頼する
戸籍の附票には、住民票上の履歴というプライバシー情報が掲載されているため、取り寄せることができる者は限られています。
ただ、弁護士等の専門家であれば取り寄せることができますし、相続に強い弁護士であれば戸籍にも精通しており、他に相続人がいないか等も一緒に調べてくれますので、弁護士に依頼することをおすすめします。
2 調査をしても相続人の行方が分からない場合
行方が分からない場合には、①不在者財産管理人を選任する方法と、②失踪宣告制度を利用する方法があります。
手続きの具体的な説明や、申立書の記載例などにつきましては、名古屋家庭裁判所のホームページにてご確認ください。
参考リンク:裁判所・家事審判事件
① 不在者財産管理人を選任する方法
調査をしても、住民票上の住所地に住んでいないなどの理由で、相続人の行方が分からない場合があります。
このような場合に、遺産分割協議を行うためには、不在者財産管理人を選任しなければなりません。
不在者財産管理人選任は、不在者の配偶者や親族、債権者等の利害関係人のほか、検察官が申立人となります。
不在者財産管理人は、家庭裁判所に許可を得た上で遺産分割協議を行うことができます。
不在者財産管理人は、親族でもなることができますが、親族がなった場合、必ずしも遺産分割協議において不在者の利益保護がはかられない可能性があるため、通常は親族が選ばれることは少ないようです。
不在者財産管理人の職務は、不在者の財産保護にありますので、遺産分割協議においても、原則として法定相続分を確保するよう協議を行うことになります。
② 失踪宣告制度を利用する方法
行方不明期間が7年間を超えている場合(戦地に臨んだ人、沈没した船舶の中にあった人、そのほかの危難に遭遇した人については、危難が去った後、1年間生死が明らかでないときも対象でとなり、これを危難失踪といいます)は、家庭裁判所に失踪宣告の申立をすることで、行方不明者が死亡した者として扱い、遺産分割協議を行うことができます。
なお、申し立てを行った後は、家庭裁判所の調査官が調査を行い、基本的には3か月以上の期間、危難失踪の場合には1か月以上の期間内に不在者や不在者の生存を知っている人にその届出をするように官報や裁判所の掲示板を用いて公示催告を行ったうえで、期間内に届出がなければ失踪宣告がなされ、申立人が市区町村役場に失踪の届出を行う必要があります。
3 相続人が行方不明の場合は相続に強い弁護士にご相談ください
行方不明の場合の対応方法は、上記のとおりとなります。
失踪宣告は、後から行方不明者が生きていることが分かった場合は、不在者本人または利害関係人が家庭裁判所に失踪宣告取り消しの審判の申し立てを行うことになりますが、失踪宣告を取り消された場合は権利関係が複雑化しますので、あらかじめ注意しておくべき要素があります。
そのため、相続に強い弁護士に相談し、リスクを検討しておくことが大切です。
名古屋やその周辺地域で相続問題にお困りの方は、弁護士法人心 名古屋法律事務所へお気軽にご連絡ください。