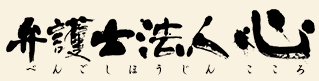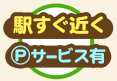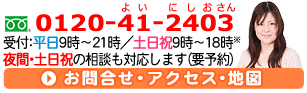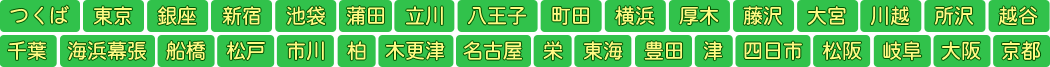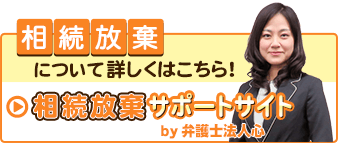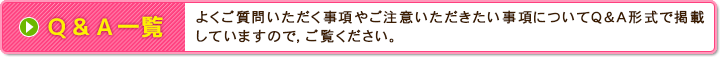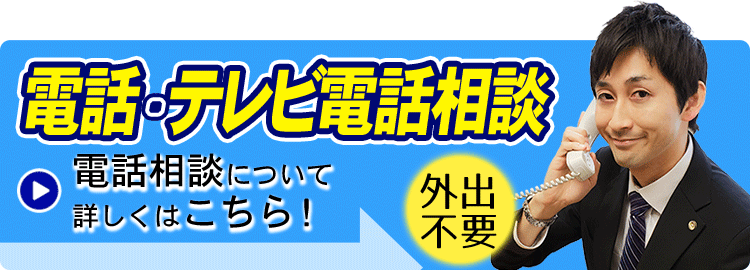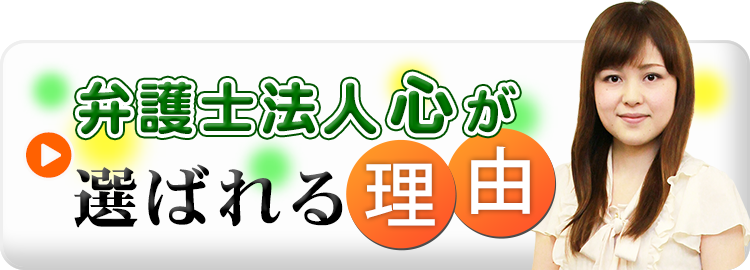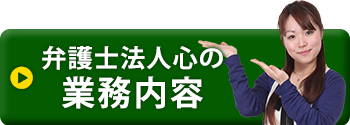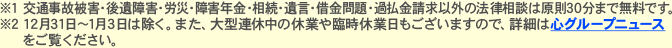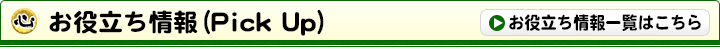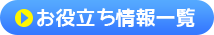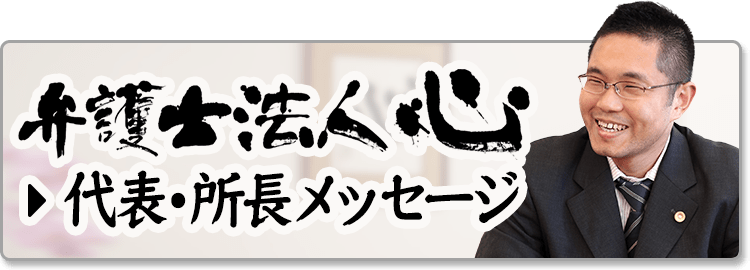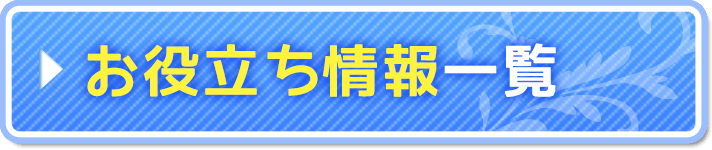相続放棄に関するご相談をお考えの方へ

1 相続放棄は弁護士にご相談ください
相続財産の中にマイナスの財産が含まれている場合、相続放棄を考える方もいらっしゃるかと思います。
本当に相続放棄を行った方がよいのか判断できない、相続放棄の手続き方法がわからないといった不安やお悩みを抱えていらっしゃる方は、弁護士にご相談ください。
相続放棄を得意とする弁護士が丁寧に相談にのらせていただきます。
まずは、弁護士法人心 名古屋法律事務所にご連絡ください。
2 相続放棄について
⑴ 相続放棄には手続きが必要
相続放棄という言葉を聞いて、皆様はどのような手続きを想像するでしょうか。
「自分は、相続をしていない」または「将来的に相続しないことを約束した」という意味で、「相続放棄をした」と言われる方は、少なくありません。
しかし、法律的には、相続放棄をするというのは、被相続人の死亡後に、家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行い、それが受理されて初めて、相続放棄をしたことになります。
⑵ その他の方法で相続分をゼロにする場合との違い
上記のように、相続放棄には手続きが必要です。
相続で相続分をゼロにしたからといって、法的に効力のある相続放棄を行えているわけではないことに注意が必要です。
例えば、自分の相続分をゼロとする遺産分割協議書に署名をしたのであれば、それは、遺産分割協議に参加をしたことになりますし、被相続人となるお父様やお母様等が亡くなられる前に、自分は相続をしないという約束をしたとしても、法的な効力は何もないということになります。
裁判所に相続放棄の申述をするのと、自分は相続をしないという内容の遺産分割協議書に署名をするのと何が違うのかと思われるかもしれません。
プラスの財産についてのみの話であれば、両者に大きな違いはありません。
しかし、プラスの財産を相続しない代わりに負債も相続しないという遺産分割協議書に署名をしたとしても、それは、他の相続人との間では有効な合意になりますが、債権者は、その協議書の内容に関わらず、法定相続分に応じて、どの相続人に請求をすることもできるのです。
その点、相続放棄の申述が裁判所に受理されていれば、債権者に対し、支払い義務がないと主張することができます。
3 相続放棄の期限
相続放棄の申述は、原則、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。
ただし、被相続人の財産状況が分からず、プラスの財産と負債のどちらが多いのか調査をしなければ相続をするか否か決められないような事情がある場合は、裁判所に申立てを行い、この期間を延ばすこともできます。
4 相続放棄をお考えの方はご相談ください
相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
例えば、被相続人が亡くなる直前、名古屋市内に住んでいたのであれば、名古屋家庭裁判所が管轄の裁判所になります。
管轄の裁判所に聞けば、手続きの方法を教えてもらうこともできますが、自分で申立てを行う場合、戸籍の取り寄せや申立書の作成等に迷われることもあるかと思います。
そのような場合には、お早めに専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
当法人にご相談いただいた場合、相続放棄を得意とする弁護士がお客様の状況をお聞きし、サポートをさせていただきます。
場合によっては弁護士だけでなく税理士などの意見も聞きながらアドバイスさせていただきますので、さまざまな状況に対応することが可能です。
名古屋で相続に関するお悩みをお持ちの方は、当法人の弁護士にご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
当法人へのお問合せについて
当法人は、平日21時までつながるフリーダイヤルよりご相談予約を承っています。相続放棄に関してお悩みの方は弁護士法人心にご相談ください。
相続放棄したほうが良いケース
1 借金が遺産よりも多い場合

プラスの財産よりも借金のほうが多い場合、
相続放棄をしなければ、相続人の財産からも借金を支払わなければならなくなり、支払えない場合は、自己破産等をしなければならなくなる可能性があります。
そのため、特別な事情がある場合を除いては、基本的に相続放棄をしたほうが良いケースが多いといえます。
なお、借金の有無に関しては、KSC(全国銀行個人信用情報センター)、CIC(株式会社シー・アイ・シー)、JICC(株式会社日本信用情報機構)といった信用情報機関で、調べることもできます。
これらでは、銀行系のローン(住宅ローン等)やキャッシング、クレジット系の契約内容、消費者金融系の契約内容を調査できますが、連帯保証人になっているかや、個人からの借り入れについては調べることができません。
2 財産を受け取らない場合
借金の有無は不明であるが、相続財産をまったく受け取らない場合は、相続放棄をしておいたほうが良いです。
理由として、相続放棄手続きを行わないと、財産を受け取らない場合であっても、借金があった場合は、借金を支払わなければならないためです。
実際、相続財産を一切受け取らなかったにもかかわらず、後日、借金が見つかり、借金の支払いを請求された事案もあります。
ここで、注意点としては、相続放棄手続きは、裁判所を通じての手続きであり、相続人間で借金を負わない旨の同意をしても、それを債権者に主張することはできません。
そのため、相続放棄をされる方は、家庭裁判所で相続放棄の申述を行うことが必要です。
相続放棄の手続きには期限がある点にもご注意ください。
3 次の順位の相続人に財産を渡したい場合
借金は特になくプラスの財産しかないが、次の順位の相続人に財産を渡したい場合は、相続放棄をしたほうが良いケースもあります。
たとえば、子、父、祖父といった家族構成で、父が亡くなりました。
子は、父の遺産を祖父に取得してもらいたいと考えています。
この場合、子が相続放棄をしなかったとき、父の遺産を祖父に渡すためには、子から祖父に生前贈与する方法が考えられます。
しかし、この場合、贈与税や不動産の贈与の場合は、不動産取得税等の税金がかかります。
これに対し、子が相続放棄をすれば、次の相続人である祖父が相続することになるため、贈与税や不動産取得税はかからなくなります。
このように、相続財産を次の順位の相続人に取得させたい場合は、相続放棄をしたほうが税金面ではよい場合があります。
なお、現在の相続人(配偶者を除く)が複数人いる場合、現在の相続人全員が相続放棄をしなければ、次の順位の相続人に遺産が行きませんので、注意が必要です。
相続放棄と遺産分割協議の関係
1 原則どちらかしかできない

遺産を分割するための協議と相続放棄は、いずれか一方のみを行うことができます。
相続放棄は、初めから相続人ではなくなる手続きです。
相続人ではないということは、遺産を取得する権利を根本的に失います。
そのため、相続放棄をした場合には、遺産の分割に関する話し合いに関わることができなくなります。
他方、遺産を分割するための協議をすることは、法定単純承認事由に該当する行為とされます。
法定単純承認事由に該当する行為とは、ひとことでいえば、相続放棄をすることが認められなくなる行為です。
遺産を分割するための協議は、遺産を取得することを前提にして行われるため、この協議を行ったということは、遺産を取得する意思があると見なされてしまいます。
遺産を取得する意思が現実化した以上、相続放棄とは相いれないこととなりますので、相続放棄をすることができなくなるのです。
2 協議をした後で相続債務の存在が明らかになった場合
実際には、遺産の分け方を協議した後になって、被相続人が多額の債務を有していたことが明らかになるということもあります。
特に保証債務などは、主債務者において自己破産などの事象が発生してはじめて金融機関から履行を求められる性質のものなので、後にならないと発覚しないことがあります。
このような場合、もしあらかじめ相続債務の存在を知っていたなら協議をしなかったという、いわゆる錯誤を理由に協議を無効にし、相続放棄が認められることもあります。
特に、協議をしたものの一切遺産を取得しなかったような場合には認められやすいです。
3 判断に悩む場合は相続放棄の期限を延長する
被相続人の生前の状況によっては、相続財産の調査がなかなか進まないということがあります。
被相続人が、不動産を複数所有しているが、ローンも複数組んでいるような場合が典型です。
不動産の価値とローン残高、どちらが高いかという調査も必要ですし、ローンについて団体信用生命保険が適用されるか否かの調査も重要なポイントとなります。
そして、財産の全貌が分からないと、遺産を取得した方が得なのか、相続放棄をした方が得なのか、判断ができません。
相続財産を把握するのに時間がかかり、相続放棄の期限までに相続放棄をすべきか判断できないような場合は、家庭裁判所に対して、相続放棄の期限の延期を申し立てることができます。
相続放棄をすべき事例
1 債務超過

相続放棄の理由として、もっとも典型的なものが、債務超過です。
亡くなられた方が生活保護等を受けていて財産がほとんどない一方で、貸金業者に借金をしていたケースや、税金等を滞納していたケースなどがあります。
また、債務の状況が不明ということも多いです。
被相続人と疎遠で生活状況を掴めていないために、どこにどのような負債が潜んでいるかわからないというケースもあります。
被相続人が亡くなった後、請求書が見つかったり、預金通帳の履歴等から負債が判明したりする場合もあります。
借金をしているはずなのに、請求書等が見つからないといった場合は、安易に大丈夫だと考えるのではなく、一度相続に詳しい弁護士にご相談ください。
JICCやCICなどの金融機関が個人の借入状況を登録している信用情報機関に問合せを行い、借金の有無を確認することができます。
相続放棄は、包括的に相続する権利(負債含む)を失う手続きであることから、負債の状況が不明であるときこそ、有効な手段となります。
2 特定の相続人に遺産を集中させる
風習や慣行によっては、家業を継ぐ相続人に全ての財産(負債も含む)を集中させるということがあります。
あるいは、一部の相続人を除き、都会に出てしまい、地元に戻る見込みがほとんどないため、実家の財産を地元に残った相続人に渡したいということもあります。
そこで、相続財産を集中させる先の相続人以外の相続人全員全てが、相続放棄をするというケースもあります。
相続放棄の利点は、相続債務も含めて特定の相続人に集約できることです。
遺産分割協議を用いた場合、財産を特定の相続人に集約することはできますが、債務については特定の相続人が全て負担すると定めるだけでは足りません。
債権者を相手に免責的債務引受契約をしなければならないのです。
これに対し、相続放棄を用いれば、このような手続きをする必要はありません。
なお、相続人のなかには、「私は相続しなくていいから」と口頭や書面で他の相続人に伝えたことで、相続放棄をしていると勘違いされているケースもあります。
これは、単に他の共同相続人に相続分を譲渡しているにすぎず、相続放棄とはなりませんので、注意が必要です。
相続放棄をご希望の場合は、必ず期限内に家庭裁判所で相続放棄の申述手続きを行ってください。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
3 他の相続人との関りを断つ
問題のある相続人がおり遺産分割協議をしたくない場合や、家族と仲たがいをしてしまい関わりたくない場合など、相続に関わらないようにする手段として、相続放棄手続を使うことができます。
相続放棄は相続人が単独で行うことができる手続きですので、他の相続人へ連絡する必要はありません。
被相続人が亡くなったことを知ったら、一人で家庭裁判所に対して手続きをすることができます。
相続放棄に必要な書類の集め方
1 必要な書類

相続放棄手続をする際は、相続放棄申述書という書類のほかにも、提出しなければならない書類があります。
必ず提出しなければならないものとして、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)、申述人(相続人)の戸籍謄本、被相続人の住民票除票または戸籍の附票があります。
直系尊属や兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍が必要となります。
兄弟姉妹の場合、両親の死亡の記載のある戸籍謄本も求められます。
その他、被相続人が死亡してから3か月以上経過後に被相続人死亡の事実を知った場合などは、その事情を裏付ける資料等を用意する必要もあります。
2 戸籍謄本類
まず、戸籍謄本は、本籍地の市区町村に対して請求します。
被相続人の除籍は被相続人の本籍地の市役所等で、申述人の戸籍謄本は申述人の本籍地の市役所等で取得します。
申述人自身の本籍地が不明である場合、住民票を取得して本籍地を確認します。
被相続人の本籍地が不明である場合、申述人の戸籍謄本の従前戸籍を確認します(場合によっては、従前戸籍から被相続人が転籍していることもあります)。
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍は、被相続人の戸籍謄本を一つ取得したら、その戸籍の記載を読み、従前の戸籍を追って取得します。
本籍地が変わっていない場合は一回ですべて手に入ることもありますが、転籍をしている場合には、複数の市区町村で戸籍を取得することになります。
被相続人の住民票除票は、被相続人の最後の住所地のある市区町村で取得します。
もし正確な住所が不明である場合は、被相続人の本籍地において、戸籍の附票というものを取得することができます。
3 その他の資料
市区町村や貸金業者からの通知によって被相続人の死亡を初めて知った場合には、その通知書のコピーを取っておきます。
また、先順位の相続人が相続放棄をした場合、その相続放棄を担当した専門家から連絡が入ることもあります。
そのような場合も、連絡に用いられた書面を保管しておき、先順位の相続人が相続放棄をした日を証明するための資料として、コピーを裁判所へ提出します。
相続放棄の期限
1 「相続の開始を知った日」から3か月以内

相続放棄の手続きを行わなければならない期限は、「相続の開始を知った日」から3か月です。
相続開始日(被相続人死亡日)とは異なるところに注意が必要です。
被相続人がお亡くなりになったのを看取った場合は、被相続人死亡日に相続の開始を知ったということになり、被相続人死亡日から3か月間が相続放棄の熟慮期間となります。
被相続人と疎遠で長年没交渉となっていたような場合で、市役所や債権者から、被相続人死亡の連絡を受けて初めて被相続人死亡を知った場合は、通知を受けた日が熟慮期間の起算点となり、ここから3か月以内に相続放棄を行う必要があります。
先順位相続人が相続放棄をしたことの連絡を受けた場合は、連絡を受けた日を以て、相続の開始を知った日となりますので、ここから3か月間が熟慮期間となります。
2 極力、相続放棄は被相続人死亡日から3か月以内に行うべき
相続放棄は、非常に厳格な期間制限があります。
この期間制限を守るために、場合によっては、夜間や土日祝日であっても、書類を裁判所に持参する必要がありますが、その際、ご依頼者様と、急ぎの打合せが必要な場合があります。
そのため、相続放棄を弁護士に依頼する場合は、弁護士がいつでも連絡がとれるよう、事務所の電話番号だけでなく、携帯電話の番号も伝えてくれるかどうかをチェックしましょう。
3 相続放棄申述の日が被相続人死亡日から3か月を超えている場合の対応
2でも少し述べましたが、相続放棄の申述を行う日が、被相続人死亡日から3か月以上経過している場合は、慎重な対応が必要です。
被相続人死亡日に(大幅に)遅れて被相続人死亡の事実を知った理由・経緯、及び熟慮期間の起算点から3か月以内であることを、裁判所に対して書面をもってしっかりと説明しなければなりません。
例えば、長年没交渉であった被相続人が借金を抱えて死亡しており、被相続人死亡日から数か月経過した後に、相続人に対して支払いの請求がなされた場合、債権者の通知書面の写し等を用い、支払い請求を受けた日が相続放棄の熟慮期間の起算点であることを示します。
加えて、もう一つ説明しなければならないことがあります。
債権者から請求を受けた日まで、被相続人が死亡したことを知らなかったという事情です。
申述人と被相続人が長年疎遠であり、没交渉であった事情も合わせて説明することになります。
相続放棄を相談する際の、弁護士の選び方
1 対応がスピーディーな弁護士に相談しましょう

相続放棄は、3か月という期間制限がある手続きです。
もし、3か月の期限を守れなかった場合、莫大な借金を相続することになってしまいます。
そのため、相続放棄の手続きで求められるのは、何よりもスピードです。
相続放棄に力を入れている弁護士であれば、緊急性が高い場合、ご契約後すぐに、裁判所に書類を持参するなどの対応が可能です。
弁護士に依頼する場合、このようなスピーディーな対応が可能かどうかが、非常に重要なポイントになります。
2 連絡がとりやすい弁護士に相談しましょう
相続放棄は、非常に厳格な期間制限があります。
この期間制限を守るために、場合によっては、夜間や土日祝日であっても、書類を裁判所に持参する必要がありますが、その際、ご依頼者様と、急ぎの打合せが必要な場合があります。
そのため、相続放棄を弁護士に依頼する場合は、弁護士がいつでも連絡がとれるよう、事務所の電話番号だけでなく、携帯電話の番号も伝えてくれるかどうかをチェックしましょう。
3 相続放棄の実績が豊富な弁護士に相談しましょう
法律の分野は幅が広く、全ての弁護士が、相続放棄の実績が豊富とは限りません。
借金を背負うことになるかどうかの、大切な問題ですので、相続放棄を依頼する場合は、相続放棄の実績が豊富な弁護士に相談することが大切です。
特に、相続放棄では、専門書にも記載されていないようなことについての知識が必要になり、相続放棄に力を入れていない弁護士では、十分な対応ができない可能性があります。
4 相続放棄専門のホームページをチェックしましょう
今では、多くの法律事務所が、ホームページを作成しています。
特に力を入れている分野については、事務所のホームページとは別個に、その分野専門のホームページを作成していることがあります。
そのため、その法律事務所が相続放棄に力を入れているかどうかは、相続放棄専門のホームページがあるかどうかが、一つの目安になります。
相続放棄の手続きにおける注意点
1 相続放棄は裁判所で行う手続きです

相続放棄の手続は、相続開始を知った日から3か月以内に、必要な書類を収集・作成し、管轄の裁判所へ提出することで開始されます。
参考リンク:裁判所の管轄区域/裁判所
手続の方法や時期は決められており、これ以外の方法で行うことはできません。
2 相続放棄を生前に行うことはできない
意外と知られていないと感じることが多いのですが、相続放棄は、被相続人がご存命のうちに行うことはできません。
補足をしますと、遺留分の放棄は生前に可能ですが、裁判所の許可が必要であり、要件も厳格です。
相続放棄は被相続人がご存命のうちにはできないにもかかわらず、相続の開始を知った日から3か月以内に行わなければならないため、時間的には非常にシビアな手続きであるといえます。
そのため、被相続人が存命のうちから相続放棄を検討しているのであれば、予め準備をしておくことはとても効果的です。
相続放棄をするにあたって、行ってもよいこと、行ってはならないことを事前に調査したり、残置物となり得る家財道具などを、被相続人の了解を得て処分しておけば、法定単純承認事由に該当する行為を行ってしまうリスクを軽減できます。
3 他の相続人に相続を放棄すると伝えても相続放棄ではない
被相続人がお亡くなりになり、他の相続人に対して相続放棄をする旨を伝えたり、何も相続しない旨の遺産分割協議を行ったとしても、法律上の相続放棄にはなりません。
このような方法を「事実上の相続放棄」と呼ぶことはありますが、法的効力はありません。
法律上の相続放棄は、管轄家庭裁判所に相続放棄申述書と戸籍謄本類等の付属書類を提出し、裁判所が相続放棄を認めて受理することではじめて成立します。
法律上の相続放棄と、事実上の相続放棄との一番の違いは、相続債務を負うか否かです。
法律上の相続放棄は、初めから法的に相続人でなかったことになりますので、被相続人の負債を負うことはありません。
他方、事実上の相続放棄は、相続人間においては相続債務を負わない旨を定めたとしても、債権者に対しては対抗できません(可分債権である金銭債権は、相続開始と同時に法定相続割合に応じて分割されます)。
そのため、別途免責的債務引受契約等を締結し、他の相続人に債務を移さない限り、相続債務を弁済する義務を負います。
4 不備のない手続きをする
相続放棄は基本的にはやり直しができない1回限りの手続きです。
そのため、ミスのないように確実に手続きを進めなければいけません。
適切に相続放棄を行うためにも、一度弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。