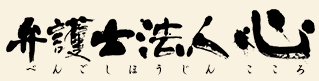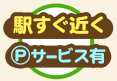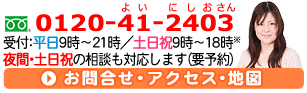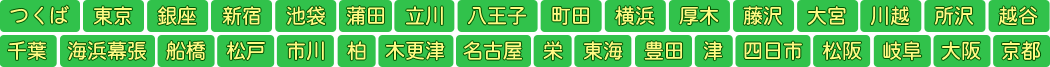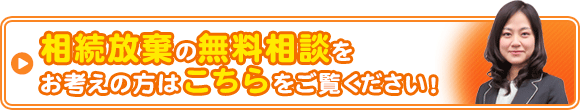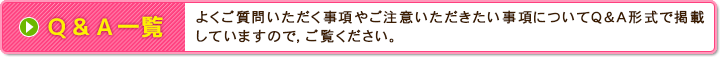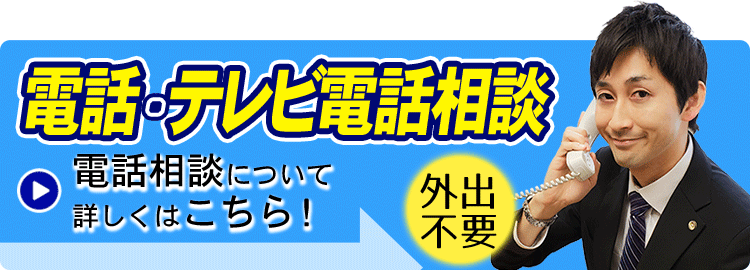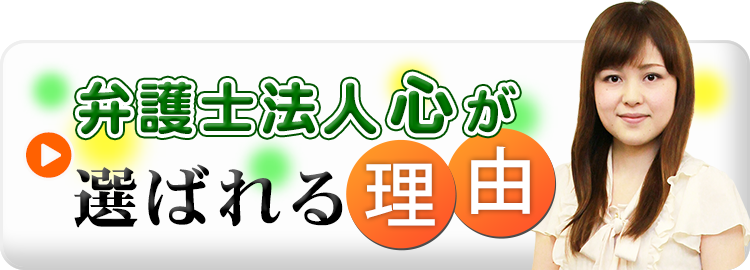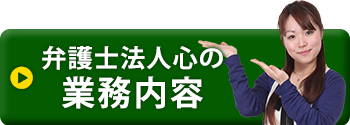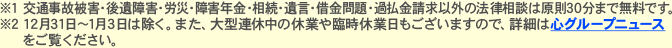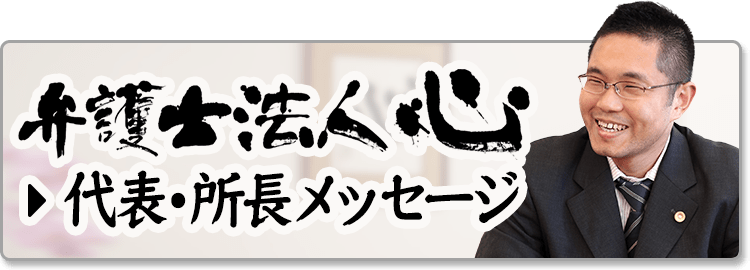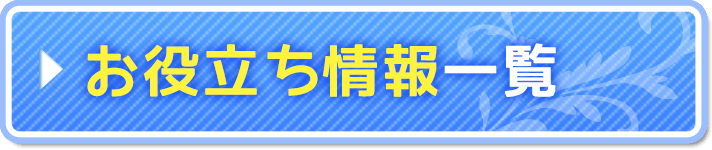相続放棄の熟慮期間
1 相続放棄とは
相続放棄とは、法律で定められた期間内に、家庭裁判所に対して相続放棄の申述書を提出することによって、相続人の財産に関する権利や義務を一切承継しないこととする制度です。
原則として相続人は、相続放棄や限定承認をしないと、プラスの財産、マイナスの財産を問わず、被相続人(故人)の一切の財産に関する権利や義務を承継します。
そのため、例えば、被相続人が生前に多額の借金していたような場合には、相続により、相続人が多額の負債を抱えることになってしまうことがあります。
これを避けるために、相続放棄を選択される方も少なくありません。
また、家の後継ぎとなる特定の相続人に相続財産を集中させたいなどの目的で、一部の相続人が相続を望まないこともあり、そのような場合にも相続放棄が行われます。
参考リンク:裁判所・相続の放棄の申述
2 熟慮期間は原則3か月
法律上、相続するか否かを決めるための期間が決まっており(この期間を「熟慮期間」といいます。)、この熟慮期間を過ぎると相続放棄をすることができなくなります。
熟慮期間は、①被相続人が亡くなったことを知り、②これによって自分が相続人であると知ったときから3か月とされています。
この間に相続人は相続財産の調査などを行い、相続放棄の必要がある場合には、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述をすることになります。
3 3か月を超えていても例外的に相続放棄をできる可能性がある
相続放棄をしなかったのが「被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたためであり、…当該相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があって、…相続人において右のように信ずるについて相当な理由があると認められるときには、…熟慮期間は相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべき時から起算すべきものと解するのが相当である」として、例外的に熟慮期間の起算点を遅らせて、相続放棄をできる可能性があることを認めた判例があります(最判昭和59年4月27日)。
例えば、被相続人には財産はないと思っていたのに、後から借金に関する通知が届いて、初めて被相続人に借金があったことを知った、という場合には、仮に亡くなったことを知ってから3か月が経っていても、相続放棄をすることができる可能性があります。
しかし、この判例は例外的に認められる可能性があることを示したものですので、必ず相続放棄が認められることを保証するものではありません。
このような場合には、専門家に相談し、今後の見通しについてご相談いただくのが良いかもしれません。
4 熟慮期間の伸長
相続財産の調査が難航するなどの事情がある場合には、熟慮期間の延長を求めることができます(これを「熟慮期間の伸長」といいます。)。
熟慮期間を延長してもらうためには、家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
この期間伸長の申立てについても、3か月の熟慮期間の間に行う必要があります。
また、熟慮期間は相続人ごとに計算されるため、期間伸長の申立ては、申し立てた相続人の熟慮期間についてのみ伸長されるものになります。
申立人以外の相続人の熟慮期間についても伸長するものではないため、ご注意ください。
何も手続きをせずに熟慮期間が経過すれば、相続人は自動的に相続を承認したものとみなされますので、注意が必要です。
5 熟慮期間中の注意点
いったん相続の承認や放棄を行うと、熟慮期間中であっても撤回することはできないので、慎重に判断する必要があります。
また、相続するつもりがなくても、相続財産を処分等した場合には、相続を承認したものとみなされるおそれがあるので注意が必要です(法廷単純承認、民法921条1号)。