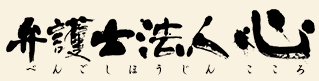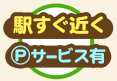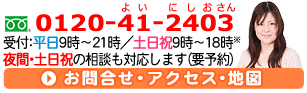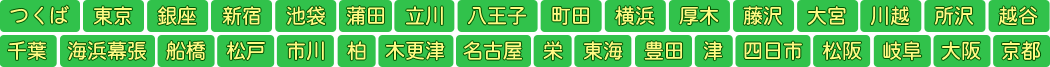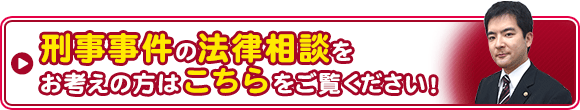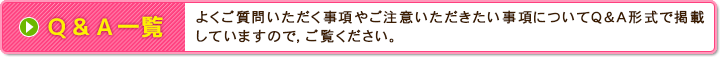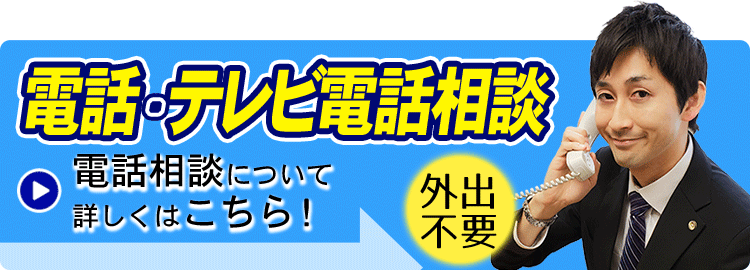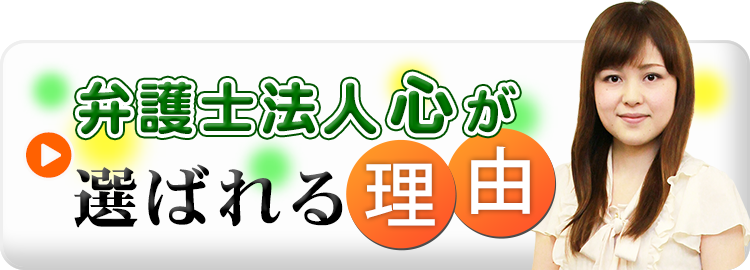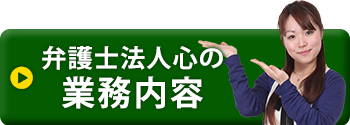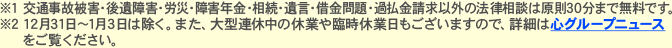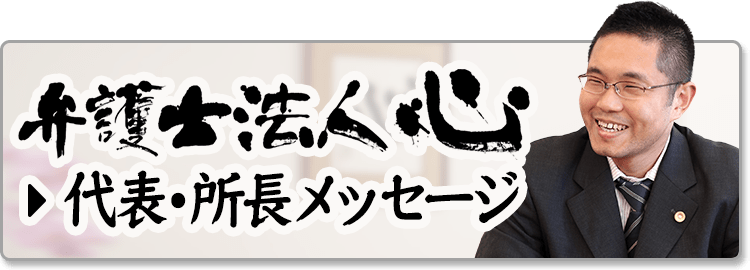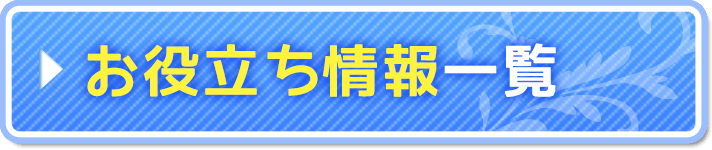裁判員裁判対象事件
1 裁判員裁判の概要
裁判員裁判とは、特定の刑事裁判において、衆議院議員選挙の有権者から事件ごとに選ばれた市民が裁判員として、裁判官とともに審理に参加する裁判制度をいいます。
司法制度改革の一環として、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」が制定され、平成21年5月21日から施行されています。
2 裁判員裁判の対象となる事件
裁判員裁判の対象となる事件は、死刑または無期の懲役または禁錮にあたる罪および故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件です。
具体的には、殺人、強盗致死傷、強姦致死傷、傷害致死、現住建造物等放火、身代金目的誘拐、危険運転致死、営利目的輸入等の薬物事犯が挙げられます。
参考リンク:最高裁判所・裁判員制度の概要
これらの事件は、市民の関心が高く、社会的にも影響が大きい重大事件であるため、市民が持つ日常感覚といったものを裁判に反映するとともに、司法に対する市民の信頼の向上を図ることを目的として裁判員裁判対象事件とされています。
3 対象事件も理由があれば裁判員裁判から除外される
裁判所は、裁判員対象事件に該当する場合でも、被告人の言動等により、裁判員やその家族に危害が加えられたり、生活の平穏が著しく害される恐れがあり、裁判員の参加が非常に難しいような場合は、裁判員裁判から除外する決定をすることができます。
被告人・弁護人は、裁判所に対し、この除外事由に該当する旨の請求ができるとともに、除外の可否について、意見を述べることができます。
もっとも、裁判員対象事件から除外されるようなケースは、ごく例外的です。
4 対象事件と非対象事件の両方の罪で起訴された場合
被告人一人に対して、裁判員対象事件と裁判員非対象事件が複数起訴されることがあります。
このような場合、裁判所は、裁判員非対象事件であっても、適当と認められるものについては、裁判員対象事件と弁論を併合して、裁判員裁判対象事件と一緒に取り扱うことができます。
一般的には、併合して審理される方が、一回の手続きで済むため被告人の利益になると考えられています。
他方で、被告人一人につき、裁判員対象事件が複数起訴されて併合された場合、一括審理をすることによる裁判員の負担が懸念されます。
そこで、特に必要があるときは、事件を分けて、裁判員を選任して、順次判決を出し、量刑の決定は、最後の判決で行うという制度もあります。
もっとも、この制度は、犯罪の証明に支障が生じるおそれがあるとき等は、利用できないと定められています。