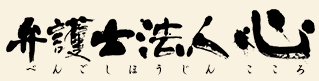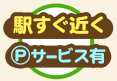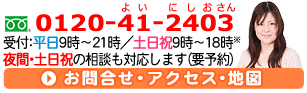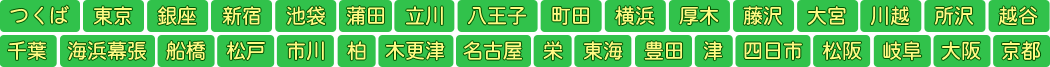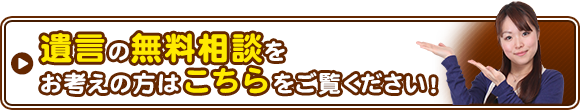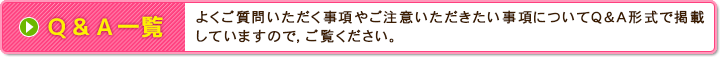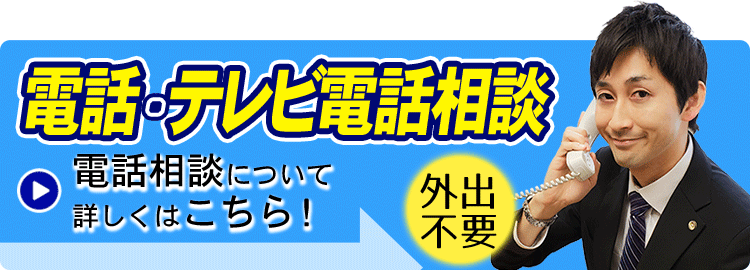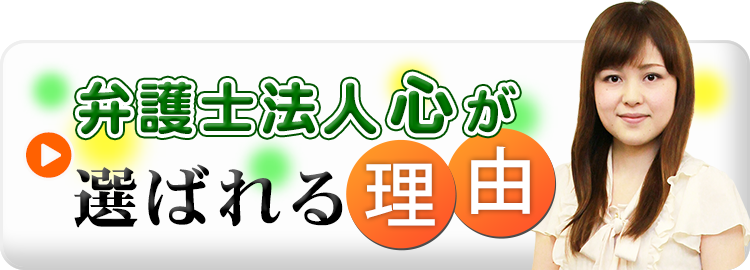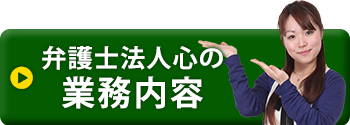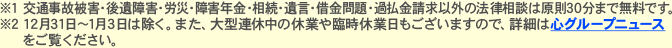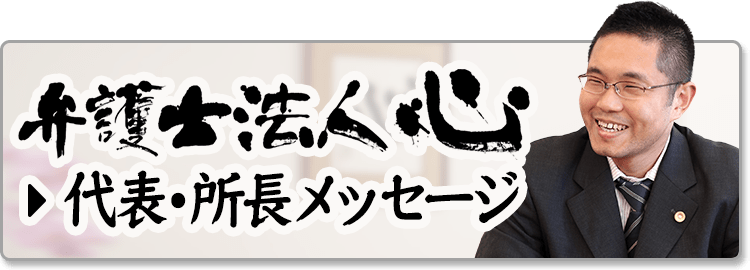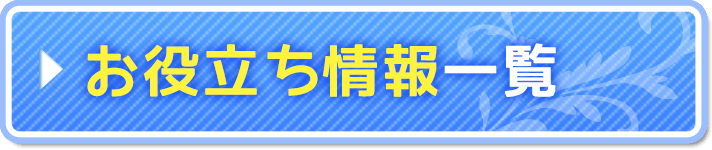遺言書を書く際のルール
1 遺言の基本的なルール
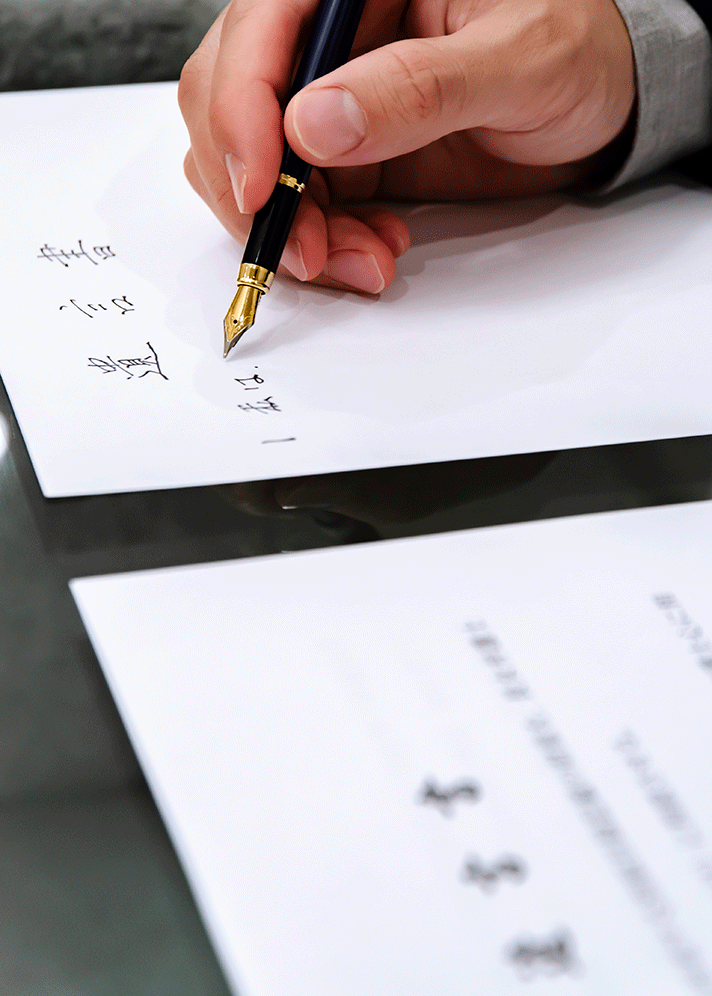
⑴ 遺言の種類
遺言は、ご自身の思いを反映した相続、遺産分けをするために、とても有効な方法です。
遺言には、ご自身で日付、名前を自署して作成する自筆証書遺言と、公証役場に赴いて公証人の目の前で内容を確認する公正証書遺言などがあります。
ここでは、自筆証書遺言のルールや、書くべき事項などをお話しします。
⑵ 書き方のルール
まず、書き方のルールとして、全文、日付及び氏名をご自身で書いて、押印することが必要です(以前はすべて手書きで書くことが求められていましたが、民法改正により、財産目録についてはパソコン等で作成できるようになりました。)。
日付については、例えば「令和4年4月吉日」などと日付が特定されていない場合、無効になるおそれがあります。
印鑑は三文判でも無効ではありませんが、後で争いにならないように、実印を使用することをおすすめします。
訂正には厳格なルールがありますので、可能な限り訂正しなくてよいように、清書前に下書きをされるとよいかと思います。
また、財産目録については、上記のとおり、パソコンを使用して作成することができるようになりましたが、その場合は、財産目録の全てのページに署名押印をする必要がありますので、ご注意ください。
参考リンク:自筆証書遺言書保管制度・遺言書の作成に当たって
2 財産の特定
また、対象となる財産の特定を正確に行う必要があります。
不動産であれば、登記簿を見て正確に所在地などを記載し、預貯金であれば、銀行名に加えて支店名や口座番号まで書いておくとよいでしょう。
十分に財産の特定ができていない場合、相続人が自分で調査をする必要が生じる可能性があるほか、場合によっては、遺言書を書いた方の希望通りの分割が実現できなくなる可能性もあります。
3 遺言執行者
加えて、遺言執行者を指定しておけば、遺言執行者以外の者が勝手に財産を処分しても無効とすることができますので、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
遺言執行者を遺言書の中で定めることは必須ではありませんが、遺言執行者を指定することで、遺言書の内容に従った遺産分割の実現をスムーズに行うことが期待できます。
遺言執行者は、個人・法人を問わず選任することができ、弁護士に依頼し選任するケースもあれば、親族や相続人を選任するケースもあります。