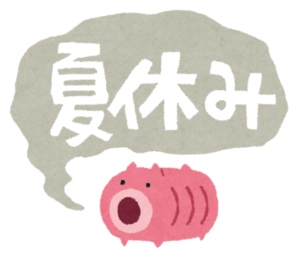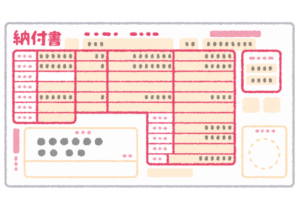弁護士法人心 本部に所属しております,弁護士の小島と申します。
日々思ったこと,皆様のお役にたてる情報などを書いていきたいと思います。
私が所属する「弁護士法人 心」のサイトはこちらです。
混沌とする所得税の改正
弁護士・税理士の小島です。
先日のブログでも令和7年の税制改正について記載しました。
基礎控除が見直され、今年の年末調整から適用されるようですので、税理士事務所では各自勉強されておられることかと思います。
なのですが、どうも準確定申告については、非常に混沌としており、誤りそうな記載がありました。
今回の令和7年度税制改正による基礎控除の見直しは、令和7年12月1日から施行するとされているため、令和7年11月30日以前に申告する準確定申告では適用されません。
なのですが、どうやら令和7年12月1日から5年以内に更正の請求を行うと、令和7年度税制改正による基礎控除の見直しの適用を受けることができるようです。
更正の請求の期限を考えると、令和12年12月2日までになるわけですが、それなら最初から令和7年の準確定申告については改正後の基礎控除額の適用させてくれよ・・・というのが税理士の本音ではないでしょうか。
準確定申告は期限があるため、あえて令和7年12月1日以降に申告するということができないケースも必ずあります。
そうなると、準確定申告をする時点で、更正の請求を行うことがセットになってしまいます。
更正の請求の申告書作成自体も、それなりに手間暇がかかるので、無料というわけにはいかない税理士事務所が多いのではないでしょうか。
とはいえ、法改正された今だけ、通常料金よりも値上げしますというのは、何ともお客様側からすると納得しづらいような・・・
最初の申告で全額還付されているようなケースであれば、そもそも更正の請求が不要なのでこれまで通りでよいかと思います。
が、最初の申告は納税→12月2日以降の更正の請求で還付になるようなケースだと、最初の納税の際にお金をとられてしばらくしたら戻ってくるという流れになるわけですから、なんとも無駄です。
還付になるのであれば、最初の申告はしなくてもいいようにも思えますが、これ、一回目の申告はあくまでも亡くなってから4か月以内に申告・納付義務が到来するので、そこで申告・納付しないと、加算税と延滞税がかかるような・・・
で、加算税と延滞税だけ納付させてから、更正の請求があったら還付する・・・?
非常に無駄な手間暇にしか思えないので、どうにかならないものなんでしょうかね。
令和7年度税制改正・・・所得税の基礎控除の見直し
弁護士・税理士・社労士の小島です。
1 変更点
所得税の基礎控除、給与所得控除の見直し
特定扶養親族特別控除の新設
2 いつから
令和7年12月1日に施行
令和7年12月の年末調整、令和7年12月以降の源泉徴収は変更後が適用される
3 基礎控除額について
これまで基礎控除額は48万円でしたが、所得金額に応じてこの基礎控除額が異なることになりました。
合計所得金額が132万円以下の場合は95万円
132万円超336万円以下の場合は88万円
336万円超489万円以下の場合は68万円
489万円超655万円以下の場合は63万円
655万円超2350万円以下の場合は58万円
となります。
ただ、88万円~63万円の控除は、令和9年分以後は58万円に引き下げられることに注意が必要です。
結局、控除額も少なく、一時的なものにすぎず、基礎控除額の見直しの効果はかなり限定的です。
4 給与所得控除の見直し
最低保障額が55万円から65万円に上がりました。
それ以外の給与所得控除額は変わりませんので、これも、ほぼすべての人には関係のない改正です。
5 特定親族特別控除の新設
居住者と生計を一にする19歳以上23歳未満の親族で合計所得金額58万円超123万円以下の人を「特定親族」とし、この特定親族がいる場合は、当該居住者の総所得金額から、特定親族1人につき最高63万円を控除する制度です。
これは、大学生が103万円超アルバイトをすると親の扶養を外れるため、親の所得税が高くなってしまうという批判を受けたものと思われます。
ただ、これも適用範囲は極めて限定的で、年齢制限があることから一過性のものであるといえます。
6 感想
政治的には、一部の政党の意見による世論の高まりを受けて、所得税の控除を増やしたように見えますが、実態としては正直ほとんど変わらないという感想です。
一度下げてしまうと、上げるときに強烈な批判を受けるので、この程度にしているのでしょうが、物価高や社会保険料負担の増額にはなにも応じず、税金の控除についてはほんのちょっぴりというのはなんとも残念な感じです。
弁護士・税理士業務とAI

ChatGPTなどの生成AIも登場し始めた当初は、よくわからない回答も多かったですが、最近リリースされているバージョンはかなり精度が高くなっています。
ただ、まだまだ怖いのがAIはウソをついてくるという点です。
裁判例や判例、条文なども、けっこうウソをついてくるので、その見極めのためには自分での調査がまだ必要になっています。
アメリカでは、実際に弁護士がAIが回答した裁判例を元に訴訟を行い、実在しない裁判例であったことを見極められずに問題になったケースもあるようです。
このような使用方法は論外かと思いますが、本当の裁判例のデータベースや法律書籍、法律論文などをすべて学習させることができれば、その分野に不慣れな弁護士が提案するよりもよほどまともな提案をするようになる時代も遠くないように感じます。
ただ、そうなったとしても、正確な現状や情報をAIに入力しなければ、正しい回答を得ることはできないということになるでしょうから、今度はAIを使いこなす側の能力が求められそうです。
私自身は、業務でExcelやVBAを使用する際に、適切な関数やプログラムを教えて欲しく、AIに聞き、税額の試算を行う表を作成したりすることに利用しています。
一昔前であれば、「ググって」行っていたことを、AIに聞くイメージですね。
ただ、この計算が本当にあっているのかという検算が必要だと思っていますので、同時に検算する仕組みを入れておかなければならないと感じてします。
AIに頼って関数やプログラムを作成すると、自分ではどこが誤っているのか気づくことができなくなってしまっているからです。
それすらも、AIが解決する時代も目の前に来ているように感じてはいますが・・・
自宅と確定申告
弁護士・税理士の小島です。
今年も確定申告が無事に終わりました。
ご依頼をいただいた皆様、ありがとうございました。
今回も、何件ものお客様から住宅ローン控除の申請についてご依頼をいただきました。
住宅ローン控除は、購入した物件にもよりますが、約10年ほど、数十万円の控除が続きますので、所得税に与える影響は大きく、住宅ローンを借り入れした際にはぜひ利用したい所得税の特例です。
ただ、こちらの特例は基本的にいわゆるZEH住宅や耐震性の高い住宅を広げたいという政策的な意図がありますので、建築されて時間の経過した中古住宅や耐震等級の低い住宅、断熱性能の高くない住宅に関しては、控除の額が少なくなっています。
いわゆる大手ハウスメーカーの場合であれば、特に気にする必要もないとは思いますが、ご心配な方は、「長期優良住宅」に該当するかどうかを尋ねられるとよいかと思います。
工務店で建てられる方の場合や、中古住宅、マンションを購入される方で、住宅ローン控除を最大限受けたい方も、同様に、不動産業者に「長期優良住宅」に該当するか否かを確認されるとよいかと思います。
なお、いわゆるZEH住宅などの優良住宅に該当するか否かは、所得税の確定申告だけでなく、家を建てる際に親や祖父母に資金を援助してもらった際の贈与税の非課税限度額にも関係があります。
これらの住宅に該当する方が、非課税枠が大きくなりますので、資金援助を受ける場合は、なおのこと、契約前に不動産業者に確認されることをお勧めします。
税理士の記帳代行はいずれなくなる?
確定申告シーズンが開始しました。
私は弁護士・税理士で、現在は税理士の業務を主に行っておりますので、確定申告はまさに最繁忙期に突入しています。
税理士事務所はどこもいまの時期は忙しいと思いますが、最近非常に強く感じるのは、税理士の主な業務でもある記帳代行、いわゆる領収証等の仕訳入力は、そう遠くないうちにAIにとってかわられるだろうなということです。
私の事務所が採用しているMJSでもAI-OCRの機能がありますし、マネーフォワードはAIと人の目を組み合わせたストリームドというサービスを提供しています。
私はまだ利用したことはありませんが、JDLのAI仕訳は非常に性能が良いとも聞いています。
まだまだ単価は決して安くありませんが、価格競争の世界なので、一気に価格も下がるだろうなということは感じています。
特に、最近出てきたChatGPTやClaude、GeminiなどのAIツールは非常に優秀ですね。
私も、いくつか自分の通帳で試してみたところ、画像から表への作成は比較的簡単に行ってくれました。
ここに仕訳をして、という指示を加えると、ほぼほぼ正確に仕訳してくれると思いますので、一気に進化が進みそうです。
会計と税法の概念
会計の世界では、発生主義と現金主義という考え方があります。
発生主義とは、現金が動いていなくても、売上や費用の支出額が確定した=発生した日を基準に計上するやり方です。
これに対して、現金主義は、現金が実際に動いた日に計上するやり方です。
会計の世界では、基本的に発生主義を基準に動いています。
これを、税法の世界では、権利確定主義という用語で説明されています。
権利確定主義とは、「収入すべき法律上の権利が確定したときの金額」が所得税法36条1項の「収入すべき金額」と解釈する考え方です。
会計の世界と矛盾がないように整合性をとっています。
実は、法律の世界では、このような権利確定主義≒発生主義のような考え方があまりないため、非常になじみにくく、所得税法を勉強し始めた学生や弁護士が最初に????と混乱する場面でもあります。
これを勉強した弁護士であれば、「ならば、色んな条件を付けた契約書を作成して、限りなく現金主義に近い形を実現しよう。」と考える方もいるかもしれません。
これは、金子先生の提唱した無条件請求権説が似たような発想で、権利確定主義の権利が確定したとは、請求にあたって受け取る側がやるべきことを全て終えて無条件に収入を請求することができるようになったとき、を権利確定とすべきという考え方ですね。
ただ、さすがに判例は無条件請求権説までは採用していないので、弁護士が契約書を理由に権利はまだ確定していないと主張する際には、慎重な判断が求められるかと思います。
もうすぐ確定申告
こんにちは。弁護士・税理士・社労士の小島です。
もうすぐ確定申告時期が到来します。
毎年、2月16日から3月15日までですが、今年は3月15日が土曜日なので、3月17日(月)が期限となります。
よく言われますのが、サラリーマンなどの給与所得者は、給与以外に20万円以上の収入がない場合は確定申告をしなくてもよいと言われます。
確かに、所得税法では20万円以下の場合、確定申告をしなくてもよいとの条文がありますので、確定申告をしなくても構いません。
しかし、実は住民税にはそのような条文がないため、給与以外の収入が20万円以下の場合でも、住民税の申告はしなければならないことになっています。
この点は、あまり知られていないため、住民税の申告が漏れている方はたびたびおられます。
住民税の申告書の作成は、各自治体のホームページに申告書が掲載されていることが多いですし、最近では、ご自身の所得を誘導に従って入力すれば、そのまま申告書が作成されるように作られているサイトもありますので、これらを利用して忘れずに申告しましょう。
なお、所得税の確定申告を行う場合は、税務署に所得税の確定申告書を提出することで、税務署から自治体に情報がいき、住民税の申告も行われますので、別途、住民税の申告書を作成する必要はありません。
自転車運転での罰則強化
道路交通法が改正され、11月から自転車運転中にいわゆる「ながらスマホ」をする行為や、酒気帯びでの自転車運転の罰則が強化されました。
ながらスマホは、これまで5万円以下の罰金であったものが、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金になりました。
さらに、ながらスマホによって交通の危険を生じさせてた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金となっています。
自転車の酒気帯び運転は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類や自転車を提供したりすることも禁止されています。
居酒屋では、自動車で来店していないかということの他に、自転車で来店していないかという点も確認が必要となりますね。
また、最近では、スマホでのレンタル自転車も増えており、私も弁護士業務や税理士業務の際に利用することがありますが、その利用の際にも、「酒気帯びではないこと」などの確認が求められるようになるかと思います。
すでに、レンタルする際にそのような確認事項を表示してタップさせるアプリもでてきていますね。
個人的には、スマホを見ながらの自転車運転は目隠し運転と同じですし、イヤホンをつけての運転は耳栓しての運転と全く同じだと思っていますので、このような危険な運転をする人が減ってくれる分には歓迎すべきかと思っています。
ノーベル賞の賞金に所得税はかかるのか?
弁護士・税理士の小島です。
50年ぶりに日本でノーベル平和賞の受賞が発表されたようです。
賞金の話をするのも下世話な感じもしますが、今回は、賞金に税金はかかるのか?という観点で記事を投稿したいと思います。
現在のノーベル平和賞の賞金は、1100万スウェーデンクローナ(約1億6000万円)のようです。
賞金も、経済的な利益であることに違いはないので、通常であれば所得税がかかるようにも思えます。
ただ、実は、ノーベル賞に基づく賞金は課税対象外になっています。
これは明確に法律上定められております。
所得税法では、第9条に非課税の規定が定められています。
ノーベル賞に関しては、同法律の第1項第13号ホに規定があり、「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」は所得税を課さないこととされています。
仮に、この規定がなかった場合、ノーベル賞の賞金は一時所得になるでしょうから、金額的にも半分近くは所得税がかかったものと思われますので、本規定の影響はかなり大きいといえます。
ちなみに、似たような非課税規定として、オリンピックやパラリンピックで特に優秀な成績を収めた者に対する表彰金なども対象となっています。
今年は9月が予定納税の引落し月
名古屋の弁護士・税理士の小島です。
個人事業主やそれ以外の方でも、個人の所得税の予定納税を毎年納付されておられる方もいるかと思います。
なかには、忘れないように口座振り替え手続にされている方もいるかと思います。
口座振替の方は、いつもは7月に引落しがされているはずなのに、今年は口座振替がなかったな?と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実は、今年は、定額減税の関係で、所得税の口座振替が9月に行われることになっています。
そのため、7月には口座振替がなかったのです。
いつもと振替のタイミングが異なりますので、銀行口座の残高を忘れずにチェックしておきましょう。
また、今年は2回目の口座振替は12月に行われます。
こちらもいつもと引落しのタイミングが異なりますので、残高には注意が必要です。
ちなみに、私自身は口座振替にはしていなかったりします。
口座振替は、納付を忘れないというメリットはありますが、税務署から納付書は送られてきますので、そうそう忘れることはないかと思います。
それよも、スマホのアプリ決済にしておくと、納税によってポイントを貯めることができます。
一回当たり30万円の納付までという制限はありますが(ただ、これも複数回にわけて納付することが可能です。)、ポイントが貯まりますので、私自身はアプリ決済で納付してます。
裁判所にも夏休みがある
あまり知られていないことかもしれませんが、裁判所にも夏休みというものがあり、8月中は夏期休廷期間が設けられています。
その間は、弁護士も法廷が開かれないため、裁判手続を行うことはできません。
すべての裁判手続を行うことができないというわけではなく、仮差押えなどの緊急性の高い案件は動いています。
また、刑事に関しては、特に関係なく休みにはなっていません。
もちろん、すべての裁判官が休みというわけではなく、部や係の単位で順番に休みをとるそうです。
とはいえ、休み中に旅行等へ行く裁判官もいるでしょうが、たまった判決を起案し、休み明けに処理ができるよう奮闘されている方も結構な数いらっしゃるようです。
これは、夏休みだけでなく、たまった休みをとることができる年末年始も同様のようです。
違う話にはなりますが、夏休みの期間には、小中学校の宿題の提出の一環として、裁判所で傍聴をする学生もいるようです。
また、最近では最高裁や、地方の裁判所でも、夏休みに裁判所見学会などのコースも用意して、そのような見学ツアーも行っているようです。
私自身が子どものころに参加したことはありませんが、確かに裁判所で妙に小さい子(小中学生くらい)がいるなと思ったことはあります。
所得税の予定納税の納付期限にご注意
名古屋の税理士、弁護士の小島です。
所得税の確定申告をされている方で、納税額が15万円を超えている方は、予定納税のお知らせが届いているかと思います。
所得税の予定納税の納付期限は、8月1日までです。
納付期限に遅れてしまうと延滞税がかかりますので、期限に遅れることのないよう納付しましょう。
期限の管理が苦手な方は、振替納税にして口座振替で自動的にさ引き落としがされるように設定されることをおすすめします。
これだと、納付期限に遅れることはありませんので管理が楽になります。
デメリット…というほどでもありませんが、他の納付方法を利用した方がお得感を感じる方法もあります。
それは、スマホアプリ納付です。
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/smartphone_nofu/index.htm
現在、PayPayや楽天ペイなど、複数のアプリ決済が可能です。
この納付方法で納めると、アプリの種類によっては支払い金額に応じたポイントが貯まるという点がメリットです。
例えば、私はPayPayで納付していますが、PayPay納付の場合、PayPayポイントがつきますので、その分ちょっとだけお得になります。
もちろん、納付期限を過ぎてしまうとできませんし、自分で納付期限を管理しなければならなくはなりますが、納付書が送られてくる間は、この方法でよいかと思っています。
なお、納付金額が30万円以下の場合でなければスマホアプリ納付は利用ができませんが、これは一回あたりの納付金額なので、複数回にわけて納付を行うことは可能です。
ですので、面倒でなければスマホアプリ納付を複数回行うことで、事実上、30万円を超える支払いも可能です。
調整給付金の申請を忘れずに
税理士・弁護士の小島です。
定額減税がスタートしましたが、さっそく、顧問先からは「やり方がよくわからない。」、「5月からスタートしてしまった。」など、様々なトラブルの声が寄せられています。
一括で給付にするか、年末調整or確定申告で対応すればよかったと思うのですが、政府の方では月次にこだわっているため、色々と私の顧問先からも疑問の声やトラブルの声があがっています。
ただ、定額減税は多くの方は関係がなく、大変なのは経理担当者、給与支払担当者、会計事務所、社労士事務所かと思います。
なのですが、「調整給付金」。こちらは、労働者の方等、一般の方に関係してくることがあります。
元々所得税がそれほど高くなかったり、扶養家族の人数が多いなどが理由で、定額減税では所得税が引き切れない場合、調整給付金の申請をすると定額減税しきれない額の給付を受けることができます。
担当する部署は、各自がお住まいの自治体になり、自治体によって取扱いの仕方が異なります。
多くの自治体では、7月下旬に対象となる方に調整給付金のお知らせを発送するようですので、そちらに書かれた手続を行う必要があります。
自治体のホームページで調べると、より正確です。
例えば、私が住んでいる名古屋市では、8月から順次案内を送付するようです。
参考:https://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000173496.html
混沌とする定額減税
名古屋の弁護士・税理士の小島です。
いよいよ6月支給分の給与から始まる定額減税ですが、どうも制度が混沌としてきました。
定額減税自体は、本人・控除対象配偶者・扶養親族の人数一人につき3万円の所得税と1万円の住民税を減税する制度です。
住民税は自治体が計算しますが、所得税の方は、給与計算を行う会社側で計算する必要があります。
確かに、これまでも月次の給与明細に反映させることが大原則で、修正等がある場合は年末調整で行うということになっていました。
しかし、実際の実務では、税額の計算と管理に手間暇がかかりすぎるうえに、この制度が今年しか行われないこともあり、年末調整で計算する予定だった会社や会計事務所もそれなりの数あったようです。
それが、本日(2024/05/21)午前の報道によると、給与明細に減税額や差引くことの出来る残りの残額を明記することを義務づける施行規則の改正を行ったようです。
定額減税は、6月支給の給与からなので、5月分の給与を計算する際には、この計算・表記をしなければならないため、既に準備を行っていたところもあったかと思います。
このような土壇場で制度の義務づけなどを行っているため、会社・会計事務所・社労士事務所の事務負担料は減税額では済まないほど生じているのが現状かと思われます。
正直、最初から給付にしておくべきだったのではないかと思わずにはいられないのですが、現場は今後も混乱が続くものと思われます。
確定申告は口座振替がオススメ
弁護士・税理士の小島です。
確定申告の期限から1か月ほど経ちましたが、実は、合法的にまだ納税をしなくてもよい方達がいます。
それは、確定申告の納付方法を「振替納税」にされている方です。
振替納税以外の場合は、所得税の場合は、申告期限と同じ令和6年3月15日までに納付する必要がありました。
ですが、振替納税にされている場合は、令和6年4月23日に引落しがなされます。
つまり、1か月以上、納付のタイミングを後ろ倒しにすることができます。
個人事業主の場合は、消費税も同様に後ろ倒しにすることができます。
令和5年分の消費税の納付期限は、令和6年4月1日でした。
ですが、こちらも振替納税の登録をされている方の場合は、令和6年4月30日が引き落とし日になっています。
つまり、約1か月ほど、納付のタイミングを後ろ倒しにすることができます。
口座振替以外の方法の場合、税理士から申告書をもらったり、納付金額を教えてもらったり、納付書を送ってもらうことで、ようやく納付をすることができます。
ただ、どうしても確定申告時期は件数が大量に寄せられるため、例えば納付期限の一か月前に納付書をお渡しする・・・などといった、余裕をもった処理は難しくなってしまいがちです。
口座振替の場合は、納付書の到着を待つ必要がありませんし、例えば平日15時までに銀行に駆け込む、といったことも必要なくなります。
なにより、納付を忘れることがありませんので、延滞税の心配をする必要もなくなります。
口座振替のメリットは大きいので、ぜひ登録されることをお勧めします。
6月から定額減税がスタート
税理士・弁護士の小島です。
確定申告はようやく終わりましたが、6月の定額減税制度に向けて、私自身、現在勉強しているところです。
定額減税は、令和5年12月の税制改正大綱で導入が公表され、とりあえずは令和6年分に関して実行されるようです。
なかみとしては、対象者は、毎月、(所得税3万円+住民税1万円)×対象となる本人や家族の人数分、税金が安くなるという制度です。
税金が安くなるという意味では、納税者にはありがたい制度ですが、個人事業主や法人の方では、対象者が誰かを6月までに把握し、計算し、毎月の給与計算に反映させなければならないため、事務負担が圧倒的に増えてしまい、非常に評判が悪い仕組みでもあります。
年末調整や確定申告の際に、一律に計算するということにした方が、よほど事務負担は軽減されるはずなのですが、どうも給与明細に反映させることで、サラリーマンに定額減税の恩恵を認識させたい、という意図を感じるような仕組みになっています。
事業規模の小さいところでは、ご自身で給与計算をしているとこもあるかと思いますが、そのようなところは、早めにご自身で勉強するか、給与計算ソフトを導入する、顧問税理士や社労士にお願いする等の対応を検討された方がよいかと思います。
国税庁のパンフレットやQ&Aも見ていますが、正直、非常に複雑に例外が設けられており、ちょっと顧問税理士に聞いたら教えてもらえる・・・ということでは済まないような仕組みになっています。
確定申告時期到来
税理士兼弁護士の小島です。
今年も確定申告時期が到来しました。
令和6年3月15日までが確定申告期限ですので、対象となる方は期限に遅れることなく申告と納税を行いましょう。
給与所得しかない方は、源泉徴収されていますので、確定申告の必要はありません。
年末調整で生命保険や住宅ローンの控除を受けている方も、特に確定申告の必要はありません。
ふるさと納税は、ワンストップ特例の適用対象となっている方は、やはり確定申告の必要はありません。
医療費控除を利用されたい方は、年末調整やふるさと納税のような特例措置がありませんので、確定申告を行う必要があります。
同一生計のご家族分をすべていれることができますので、ご家族全員の医療費をまとめておき、10万円を超えるような場合は、医療費控除を申請することで源泉徴収された税金が還付される可能性があります。
※その年分の総所得金額が200万円以下の場合は、医療費の合計が10万円以下の場合でも医療費控除が利用できる場合があります。
医療費は、医療機関で支払った治療費の他にも、その医療機関への交通費も入れられますので(タクシー代は原則としてNG、ガソリン代はNGです。)、それらの領収証や記録を残しておくことも有益です。
電子帳簿保存法がスタート
1月1日から、電子帳簿保存法がスタートしました。
帳簿書類や経理書類の電子化が、スキャナ保存が・・・などと騒がれていた法律ですが、大きく変わる点としては、電子で送られてくる請求書や領収書等を電子で保存する必要がある、という点です。
今ある紙の領収書や請求書をすべてスキャンしてデータで保存することまでは求められていません。
ただ、アマゾンや楽天などのWebの通販サイトで購入し、領収書が紙で送られてくることはなく、電子データでメールで送られてきたり、自らサイトにアクセスしてダウンロードするようなサイトの場合は、PDF等の電子データでの保管が義務づけられることになります。
これまでは、そういったサイトからダウンロードしたうえで印刷して保管されていた方もおられたと思いますが、1月1日以降から、印刷して保管するという方法ではNGとなりました。
実務的には、これが業務効率化に資するかというと、むしろ逆です。
すべての請求書・領収書がデータで送られてくるようであれば、この方法で構わないと思いますが、現実的には、中小企業の間では、ほとんどが紙で請求書を送ったり、FAXで送受信していたりするなどしており、紙をなくすことができていません。
弁護士も、書籍を購入した際など、紙で領収証を渡されます。
結果として、紙とデータの二重管理にならざるをえず、探す際には両方を探す必要がでてくるため、面倒になったな、というのが正直なところです。
インボイス対応は大変
10月から始まったインボイスが早くも2か月ほど経過しました。
お客様からも色々とお問い合わせを受けますが、実務上もけっこう手間暇が増えて大変です。
本則課税事業者の場合、一部の例外を除いて、どれだけ細かい領収書や請求書であったとしても、インボイス対応ができているかどうかを判別する必要があります。
また、一見、Tからはじまる登録番号が書いてあり、インボイス対応しているようにも見えるものもありますが、よくよく見てみると、税率や税額が書いていないため、インボイスの要件を充たしていなかったり、チェックする経理担当者はかなり手間暇が増えています。
インボイスが不要で帳簿への記載のみでよいとされている特例もありますが、帳簿記載要件を充たすためには、ほぼすべての仕訳の摘要欄やメモ欄にその要件を充たすための記載事項を書かなければならず、かえって手間が増えるため、インボイスを発行してもらった方が圧倒的に楽だったり、制度矛盾ではないかと思えるようなことも起きています。
弁護士業務のなかでは、お客様が一般個人の方の場合は、全く関係がありませんが、企業法務を行う上では関係してきます。
インボイスは求められたときに発行すればよい、とはされていますが、正直、対応の手間が多すぎ、ここまでの要件を定める必要があったのか・・・?と疑問に思います。
任意後見のメリット
成年後見のデメリットは、本人にかわって財産を管理する成年後見人が家庭裁判所によって勝手に選ばれてしまうという点にあります。
上申という方法で、家族の誰かや知り合いの信頼できる弁護士等に成年後見人になってもらう方法もありますが、最終決定権限は家庭裁判所にありますので、必ずしも指定した人物が成年後見人になることができるわけではありません。
また、毎月おおむね2万~5万円の成年後見報酬が本人の財産から支払われることになります(※各地域の家庭裁判所や本人の財産状況等によって額は変わります。)。
ご家族からすると、知らない人に本人の財産を管理されたうえに毎月目減りしていく感覚となってしまい、抵抗感があるのが実情です。
これに対し、任意後見人は、本人があらかじめ自由に選んでおくことができますし、報酬もあり・なし含め自由に決めることができます。
デメリットとしては、本人が元気で判断能力がある間でなければ、選ぶことができないこと。
任意後見人にも、それを監督する任意後見監督人が選ばれるということです。
ただ、任意後見監督人の報酬は、成年後見人の報酬よりも低いことが多いようですし。任意後見人にお願いする管理内容をあらかじめ自由に決めておくことができるという点は大きなメリットです。